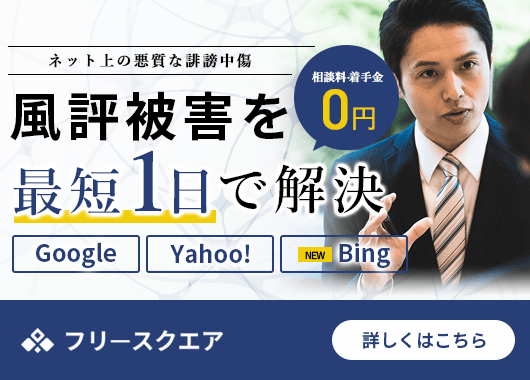「売上ナンバーワン」「人気No.1」「満足度100%!」などのNo.1表示は、企業の広告や販促物において魅力的なキャッチコピーとして使用されています。
企業の商品やサービスに対する信頼感を高め、購買行動を後押しする強力な訴求手段となりますが、根拠が不十分なまま使用すると、景品表示法に違反する可能性がある点に注意が必要です。
実際に「No.1」と訴求した広告を巡って、行政指導や措置命令を受けた企業も存在しており、表現方法には十分な注意が求められます。
本記事では、「売上ナンバーワン」の使用が問題とされる具体的なケースや、適法に使用するためのポイント・対処法について詳しく解説します。
「売上ナンバーワン」は使用しても大丈夫?

「売上ナンバーワン」といったNo.1表示は、一定の条件を満たしていれば広告や販促物に使用することが可能であり、実際に多くの企業が「売上No.1」「顧客満足度100%」「利用者数No.1」といった表現を使用しています。
ただし、No.1表示が「合理的な根拠」に基づかず、事実と異なる場合には、実際のものまたは競合他社のものよりも著しく優良または有利であると一般消費者に誤認させる優良誤認表示または有利誤認表示として、景品表示法に違反するおそれがあります。
そして、「合理的な根拠」に基づくものといえるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
- No.1表示の内容が客観的な調査に基づいていること
- 調査結果を正確かつ適正に引用していること
したがって、たとえば、以下のようなケースは特に注意が必要です。
- 独自の集計や一部地域での売上を「全国1位」のように拡大解釈してアピール
- 調査方法や調査期間、比較対象が明示されていない
- 実際の利用者に対する調査ではないなど客観性に欠けるデータを根拠としている
このようなケースでは、消費者に「最も売れている商品である」と誤認させる恐れがあるため、客観的なデータに基づいた明確な根拠を示す方法をとり、表示の仕方にも十分に配慮することが重要です。
「売上ナンバーワン」の効果
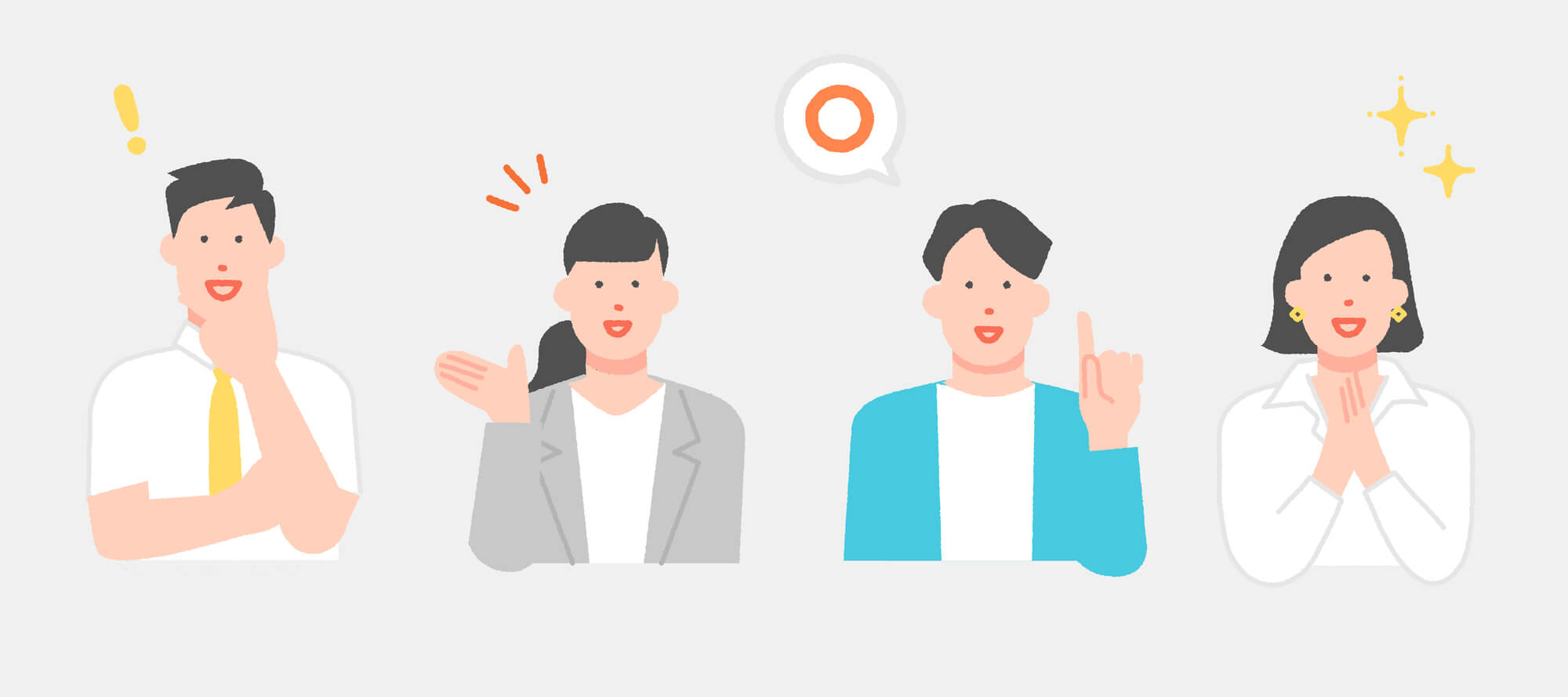
「売上ナンバーワン」というフレーズは、企業のマーケティングや広告において非常に高い訴求力を持つ効果的な方法の一つです。
企業が「売上No.1」「利用者数No.1」を用いることで、消費者に対して「多数の利用実績がある」「多くの人に選ばれている」といった印象を与え、商品やサービスに対する信頼感を高めることができます。
特に新規顧客にとっては、どの商品やサービスを選ぶべきか迷っている際に、「売上No.1」と記載されていることで品質や実績の裏付けがあると感じやすくなり、購買の後押しにつながる傾向があります。
また、競合他社と比較する場合も、「売上ナンバーワン」というフレーズは企業や商品の優位性を端的に示す表現として有効です。限られた広告スペースや短い訴求時間の中でも、瞬時に訴求力を発揮できる方法としても大きな魅力といえるでしょう。
ただし、このような強力な効果があるからこそ、景品表示法においても厳しい基準が設けられていることを理解し、根拠のある正しい使い方を心がけることが重要です。
「売上ナンバーワン」の主な効果▼
- 消費者に安心感と信頼感を与える
- 新規顧客の購買を後押しする
- 競合他社との差別化になる
景品表示法とは?

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者が商品やサービスを選ぶ際に、誤認したり不利益を被ることを防ぐための法律です。
以下は、消費者庁が公表している景品表示法の説明文です。
景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
参考:消費者庁
このように、景品表示法は表示内容の正確性と景品の適正性を保つことを目的としており、消費者保護と公正な競争の両立を図るための重要な法律です。
特に「売上ナンバーワン」「人気No.1」などのフレーズは、消費者に与える影響が大きいため、表示の根拠や正当性が厳しく問われる傾向があります。
「売上ナンバーワン」はどんな場合にNGになる?良くある違反例を紹介

「売上No.1」「人気No.1」「満足度No.1」などのNo.1表示は、商品やサービスの信頼性を高めるうえで非常に効果的な方法です。しかし、その強い訴求力ゆえに、消費者に誤解を与えるリスクが高く、景品表示法の観点からも特に注意が必要な表現とされています。
客観的根拠のない「自社集計」に基づく表記
「売上ナンバーワン」というフレーズを用いる場合、自社が独自に集計・算出したデータを根拠として使用するケースは少なくありません。
たとえば、「当社調べ」「当社販売実績に基づく」といった注記を添えてNo.1表示を行うパターンです。
しかし、自社のみの集計結果は、客観的な比較や市場全体の中での相対的な優位性を示すものではないため、消費者に対して実際のものまたは競合他社のものよりも著しく優良または有利であるとの誤認を与える可能性があります。
特に、他社と比較した「業界1位」「全国No.1」などの表現を用いる場合は、中立性の高い第三者機関の調査データや、業界全体の統計などが必要とされます。
また、自社内で最も売れている商品に対して「売上No.1」と表示するなど、比較対象が存在しない状態でのNo.1表示も、消費者に誤解を与えるおそれがあるため注意が必要です。
景品表示法においては、根拠の信頼性と客観性が非常に重要視されるため、単に「自社で一番売れている」ことを理由にNo.1と表示するのは避けた方が良いでしょう。
限定的なデータをあたかも全体の結果のように表示
「売上ナンバーワン」というフレーズを使う場合において注意が必要なのが、一部の地域・期間・店舗などに限定されたデータを、全国的または業界全体の結果であるかのように表示してしまうケースです。
たとえば、ある地域や特定の店舗でのみ売上1位を獲得した実績があったとしても、その事実を明確にせず、「売上No.1」とだけ記載してしまうと、全国や業界全体において1位であると消費者が誤認するおそれがあります。
このような場合、表示の範囲(地域・期間・条件など)を明確に示さないことが、優良誤認表示に該当する原因になります。
調査対象・調査期間・比較対象が明示されていない
「売上ナンバーワン」と記載する場合、その根拠となる調査の内容が具体的に示されていないと、消費者に誤解を与える可能性が高くなります。
特に以下のような情報が欠けていると、景品表示法上の違反と判断されるおそれがあります。
- 誰に調査を行ったのか(調査対象)
- どの時期のデータを使用したのか(調査期間)
- 何と比較して1位となったのか(比較対象)
消費者庁が発表している違反事例においても、調査の範囲や方法を明示していない広告表現が、優良誤認に該当したと判断されるケースが複数存在しています。
NO1表示で行政処分された企業の事例を紹介

「売上No.1」や「人気No.1」などのNo.1表示を用いた広告は、企業や商品の実績を強調するうえで非常に有効な訴求方法ですが、根拠が不十分なまま使用された場合は、景品表示法違反とみなされ、行政処分の対象となることがあります。
実際、過去には複数の企業が「No.1」広告を理由に、消費者庁から措置命令などの行政処分を受けた事例が報告されています。
太陽光発電2社が「No.1」表示で景品表示法違反に(2024年2月)
2024年2月27日、消費者庁は新日本エネックス及び安心頼ホームに対して、景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当するとして措置命令を出しました。
新日本エネックスは自社サイトにて「アフターフォローも充実の太陽光発電蓄電池販売No.1」「安心して導入できる太陽光発電・蓄電池販売No.1」などと表示していました。
調査はJMR社に委託されたものでしたが、実際に商品・サービスを利用したかどうかを確認せず、印象のみを問う内容だったため、客観性を欠いた不適切な根拠であるとして、「実際よりも著しく優良」と誤認させる表示であると判断されました。
また、安心頼ホームは自社サイトで「九州エリア口コミ満足度No.1」「信頼の3冠獲得 第1位」などといった表現を掲載していました。しかし、根拠とされた調査は特定の9事業者だけを恣意的に抽出し、サイトの印象を比較した内容であり、実際にサービスを利用した消費者の評価に基づくものではなく、「実際よりも著しく優良」と誤認される表示と判断されました。
No.1表示で業務停止命令|健康食品販売の(株)サンに特定商取引法違反(2024年3月)
2024年3月15日、消費者庁は健康食品「Platte(プラッテ)」を通信販売していた株式会社サン(東京都新宿区)に対し、特定商取引法違反により3か月間の業務停止命令と指示処分を行いました。代表取締役・峯岸直樹氏にも同内容の業務禁止命令が科されています。
「ダイエットドリンクNo.1」「10冠達成」などと広告表示していましたが、調査は実際に商品の利用者を対象としたものではなく、公平・公正な調査ではないとして、合理的な根拠のないNo.1表示と認定されました。また、商品ページにおいて、契約内容(価格、数量、支払・解約条件など)を十分に表示せず、消費者が誤認するような手続き誘導をしていたとされます。
このように、No.1表示が通信販売の場面で使用される場合、景品表示法に加え特定商取引法(誇大広告規制)が適用され、業務停止命令などのより重い行政処分を受けることがあります。
「No.1表示に根拠なし」株式会社バンザンに6,346万円の課徴金命令(2023年8月)
2023年8月1日、消費者庁は株式会社バンザンに対し、景品表示法に基づく課徴金納付命令を出しました。対象となったのは、同社が提供する「メガスタ高校生」「メガスタ中学生」「メガスタ私立」のオンライン個別指導サービスに関する広告表示です。
同社は、自社ウェブサイトやパンフレット、動画広告などで「利用者満足度No.1」や「口コミ人気度No.1」などと繰り返し表示していましたが、実際にはこれらの順位を示す根拠となる調査に客観性がなく、利用者による評価でもありませんでした。また、「返金保証」「成績保証」などの制度について、あたかも期間限定であるかのように表示していたものの、実際には期限後に申し込んだ場合でも適用されており、表示内容と実態が異なっていました。
これらの表示は、消費者に対して実際よりも優れたサービスであると誤認させるおそれがあるとして、景品表示法違反に該当すると判断されました。株式会社バンザンには、合計6,346万円の課徴金が命じられました。
適正と認められやすい「売上ナンバーワン」の表示方法は?

まず最も重要なのは、「客観的なデータ」に基づいていることです。自社の調査や一部ユーザーの声だけを根拠にしたNo.1表示はNG。第三者機関などの調査で、明確な調査方法・調査対象・調査期間が定められている必要があります。
さらに、利用者が誤認しないよう、調査の出典や調査時期を明記することも不可欠です。「全国〇人を対象とした〇年〇月の〇〇リサーチ調べ」など、出典元の記載がなければ、合理的な根拠のないNo.1表示とみなされるリスクがあります。
適切と判断される可能性が高い例▽
「2025年4月 全国の〇〇1,000名を対象にした調査(〇〇リサーチ調べ)において、オンライン〇〇サービス利用満足度 No.1」
→ 調査機関・対象・時期・項目がすべて明示されており、根拠が客観的であるため適正と判断される可能性が高いです。
景品表示法に違反する可能性がある例▽
「利用者満足度No.1!」「圧倒的人気No.1!」
→ 出典や調査条件が一切記載されておらず、消費者に「他社より明確に優れている」と誤認させる可能性があります。こうした表現の方法によっては、景品表示法に違反すると判断され、行政処分の対象となることがあります。
「売上ナンバーワン」で気をつけたいポイント

ここでは、「売上ナンバーワン」と表示する際に注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
定期的に根拠となるデータを見直す
企業が「売上ナンバーワン」を用いる場合は、その根拠となるデータが常に最新で正確であることが求められます。仮に過去のデータで一時的に1位だったとしても、現在の状況と乖離しているままその内容を広告に使用し続けてしまった場合、不当表示と判断されるおそれがあります。特に市場の動きが早い業界では、数か月で順位が変動することも珍しくありません。そのため、「No.1」と記載している場合は、調査時期や出典を明記するだけでなく、定期的に売上データや調査結果を見直し、内容が事実と一致しているかを確認することが非常に重要です。
広告代理店・制作側とも連携を徹底
たとえ第三者機関による調査で「売上ナンバーワン」などの事実が認められていたとしても、その情報を広告やLPに反映する際に、適切な表示ルールを守らなければ、優良誤認または有利誤認と判断される可能性があります。例えば、調査の対象期間や調査方法、調査主体の明示が抜け落ちたまま「No.1」と記載された場合、根拠のある実績であっても違反とみなされるおそれがあります。こうしたリスクを回避するためにも、広告代理店や制作会社など、クリエイティブ制作に関わるすべての関係者と連携し、表示内容が法令に準拠しているかどうかをしっかり確認する体制を整えることが重要です。
法務や弁護士への事前確認
「売上ナンバーワン」などの表記を広告に活用する際は、事前に法務部門や弁護士に内容を確認してもらうことが重要です。たとえ実績に裏付けがあったとしても、表示方法や文言の選び方ひとつで、景品表示法違反とみなされるリスクがあります。特に、第三者の調査結果を引用する場合や、消費者の誤認につながりやすい表現を含む場合は、法的な観点からのチェックを経ることでトラブルの未然防止につながります。リリース前の最終確認として、専門家の視点を取り入れることは、ブランドを守る上でも非常に有効です。
まとめ
「売上ナンバーワン」「人気No.1」といったNo.1表示は、企業の広告や販促において強力な訴求力を持つ一方で、使い方を誤れば景品表示法違反となり、行政処分のリスクも伴います。
No.1表示を使用するためには、客観的で信頼性の高いデータに基づくことが大前提です。また、調査の出典・対象・期間などの明示も必須となります。自社調べや恣意的なデータに基づくNo.1表示は、たとえ事実であっても違反とみなされる可能性があるため要注意です。
No.1表示は使い方次第で企業の大きな武器となります。ルールに則った正しい利用を心がけ、信頼されるブランディングと継続的な成果につなげていきましょう。