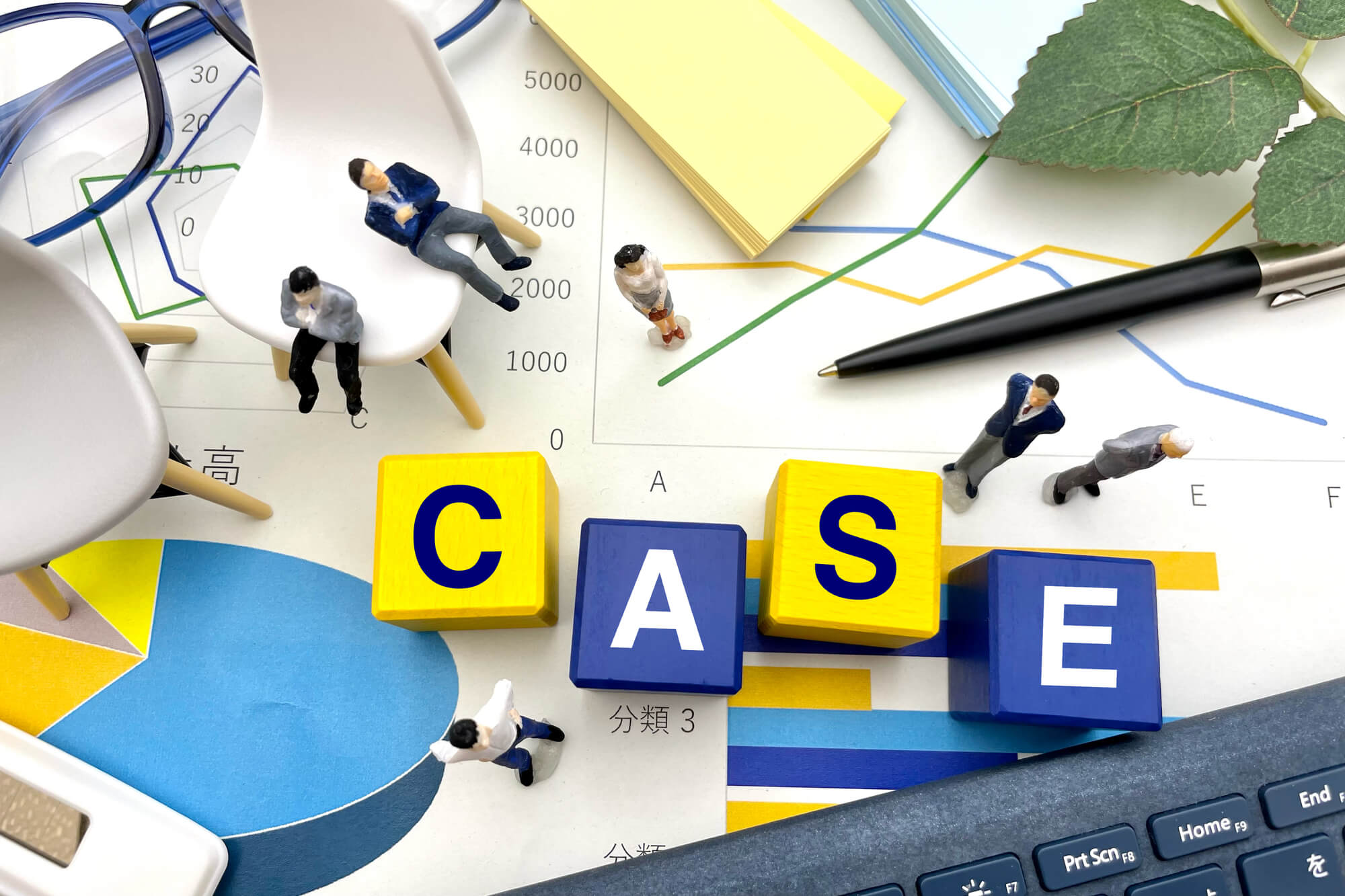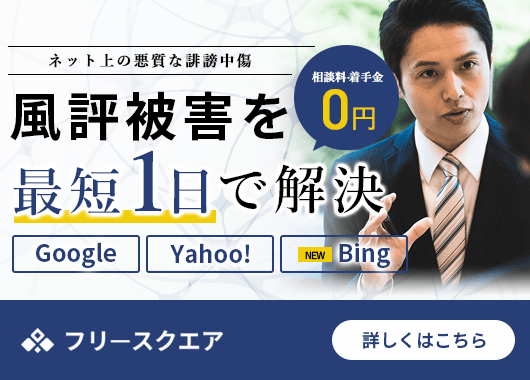SNSやネットの掲示板など、インターネット上での書き込みや発言は、今では多くの人にとって身近なものとなりつつあります。
しかし、気軽に書き込んだ一言が「誹謗中傷」とみなされ、名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪に問われるケースも少なくありません。
「批判のつもりだったのに…」「ただの感想が訴えられるの?」
このように、どこまでが許される意見で、どこからが誹謗中傷なのかは非常にあいまいで、誤解しやすいポイントです。
本記事では、
- 誹謗中傷とはそもそも何か?
- どこから違法になるのか?
- 名誉毀損罪・侮辱罪の成立条件は?
といった疑問に、法律の観点から解説します。
万が一、自分が誹謗中傷の被害に遭った場合の対策も紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも「誹謗中傷」とは?

誹謗中傷とは警察庁によると、「悪口や根拠のない嘘等を言って、他人を傷つけたりする行為です」と説明されています。正当な批判や意見との線引きが難しい場面もありますが、近年では、匿名でのネット上の書き込みやDM(ダイレクトメッセージ)が原因で、深刻な被害へとつながるケースが増えています。これに伴い、警察や弁護士に相談する人も年々増加しています。
社会的に正当な批判や意見表明であれば「表現の自由」として守られる場合もあります。
しかし、その内容や伝え方によっては、相手の名誉や社会的評価を著しく傷つけ、名誉毀損罪や侮辱罪といった刑事罰の対象となるおそれがあります。
「誹謗」と「中傷」の違い
「誹謗中傷」はひとつの言葉として使われることが多いですが、実は「誹謗」と「中傷」は意味が少し異なります。
- 誹謗:相手の悪口を言うこと
- 中傷:根拠のないことを言いふらして、その人の名誉を傷つけること
つまり、誹謗は事実ベースの攻撃である一方、中傷は根拠のない嘘やデマを含む場合に使われる傾向があります。
なお、法律では「誹謗」「中傷」という言葉は直接使われず、名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪に該当するかどうかで判断されます。
批判と誹謗中傷はどう違う?|知っておきたい境界線
SNSやネット上では、ある人物や企業に対する意見や書き込みが、「正当な批判」なのか「誹謗中傷」なのか、判断が難しいケースも少なくありません。しかし、両者の間には明確な違いがあります。
批判とは、物事に対する意見や問題点を指摘する行為で、異なる立場から意見を述べることも含まれます。
事実に基づき、意見を述べるものであれば、「表現の自由」として認められます。
一方、誹謗中傷は、相手を傷つける目的で、侮辱や悪口、根拠のないデマなどを発信する行為を指します。内容や表現次第では、名誉毀損罪や侮辱罪として扱われることもあります。
批判と誹謗中傷の境界線のポイント▼
- 批判:公共性があり、事実に基づき、意見を述べている
- 誹謗中傷: 私的感情による攻撃、根拠のない悪口や侮辱、嘘やデマの流布
自分の発言が「正当な批判」のつもりでも、表現が攻撃的・人格否定的になると誹謗中傷とみなされる恐れがあるため、注意が求められます。
SNSやネットで起きやすい誹謗中傷の特徴
SNSやネット上での誹謗中傷は、日常的な投稿や批判の一部として見過ごされやすく、本人に悪意がない場合でもトラブルを招く恐れがあります。
特にSNSやネットには、以下のような特徴があり、誹謗中傷の被害を深刻化させやすいとされています。
- 拡散力があり一気に広まる
- 匿名で投稿できる
- 投稿がスクリーンショットなどで記録として残る
SNSやネットでの誹謗中傷を含む書き込みや発言は、思わぬ形で拡散・記録され、被害者にとっては大きな精神的・社会的ダメージとなりやすいのが実情です。
特に、批判と誹謗中傷の境界があいまいな書き込みは注意が必要です。
「これって誹謗中傷にあたるの?」と感じた段階で、早めに専門家に相談することで、被害の拡大を防げる場合があります。
誹謗中傷はどこからが違法になる?民事・刑事での判断基準を整理

ネット上の発言や書き込みは、表現の自由として一定の範囲で認められていますが、内容や表現方法によっては、たとえそれが「批判」のつもりであっても、法的責任を問われるリスクがあります。
誹謗中傷が問題となる場面では、主に以下の2つの観点で違法性が判断されます。
- 民事上の違法性(損害賠償責任)
- 刑事上の違法性(名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪行為)
また、何気ない発言でも、文脈や意図次第で違法とされることもあります。
ここでは、誹謗中傷が民事・刑事のどのような基準で法的責任を問われるかを整理します。
民事上の違法(損害賠償責任)
SNSやネット上で誹謗中傷を行った場合、被害者から損害賠償を請求される可能性があります。
これは、民法上の「不法行為」に基づく請求であり、刑事罰とは異なり、被害者の損害を金銭で補償することを目的としています。
一般的には、名誉毀損によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを求められることが多く、加害者にとっては大きな負担となることもあります。
ネット上での投稿が以下のような条件を満たすと、民法上の「不法行為」と認められ、損害賠償請求が成立する可能性があります。
- 社会的評価を低下させるような内容であること
- 発言が公開され、多数の人の目に触れる状態であること
- 違法である(公共性・公益性・真実性がない)こと
- 被害者が精神的・経済的損害を受けたと認められること
- 加害者に故意または過失があること
たとえば、「〇〇は詐欺をしている人だ」「〇〇は高校時代にいじめをしていた人だ」といった対象者の社会的評価を低下させるような内容をSNSに投稿すれば、たとえ内容が真実であっても、公共性や公益性が認められない限り違法となります。
なお、損害賠償の内容には慰謝料や弁護士費用、削除請求にかかる費用なども含まれることがあります。
刑事上の違法(犯罪行為)
誹謗中傷の内容や文脈次第では、刑法上の「犯罪行為」として扱われることがあります。
特にSNS上の書き込みでは、「名誉毀損罪(事実の摘示によって名誉を傷つける)」や「侮辱罪(侮辱的な表現によって名誉を傷つける)」が問題になります。
いずれの犯罪も、ポイントは、「公然と(多くの人が見る状況で)」「相手の社会的評価を下げる表現」をしたかどうかです。
たとえ匿名でも、これらに該当すれば捜査対象となり、起訴・有罪によって前科が付くこともあります。
※刑事罰は、違法性・悪質性・公共性の有無などを総合的に判断して決まります。
「名誉毀損罪」と「侮辱罪」の詳細な判断基準は次章で解説します。
名誉毀損罪・侮辱罪とは?成立要件を解説

NSやネット上での誹謗中傷が「刑事事件」として扱われる場合、特に問題となるのが 名誉毀損罪(刑法230条) と 侮辱罪(刑法231条) です。
名誉毀損罪と侮辱罪はどちらも他者の名誉を害する可能性のある行為を対象としていますが、その成立条件と扱われ方には違いがあります。
この章では、それぞれの罪がどのような要件で成立するのかを解説していきます。
名誉毀損罪の成立条件
名誉毀損罪は、刑法第230条に規定されており、公然と他人の社会的評価を下げるような事実を摘示した場合に成立する犯罪です。
たとえ発言の内容が真実であっても、公共性や公益性が認められない場合には処罰の対象となる可能性があります。
名誉毀損罪が成立するには、主に以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 公然性があること
不特定多数の人が知ることができる状態で発言された場合を指します。
SNSや掲示板への投稿、YouTubeなどの発言もこれに該当します。 - 事実の摘示があること
「〇〇は不倫している」「〇〇は脱税している」など、具体的な事実を示す内容である必要があります。事実でなく侮辱的な感情表現(例:バカ、無能など)は侮辱罪に該当します。 - 他人の名誉を毀損する内容であること
ここで重要なのは、内容が真実かどうかではなく、それを公表することで他人の社会的評価が下がるおそれがあるかどうかという点です。
つまり、その情報が広まることで、該当する人物の信用や評価が損なわれるかが判断基準となります。
侮辱罪の成立条件
侮辱罪は、刑法第231条に規定されており、公然と他人を侮辱することによって、その人の名誉を傷つけた場合に成立する犯罪です。
ここでいう「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態を指します。
たとえば、ネットの匿名掲示板やSNSでの発言は、多くの人が閲覧できるため、「公然」にあたるとみなされます。
侮辱罪の成立には、人の社会的評価を低下させるような言動が必要です。
これには、相手の名誉を傷つける意図的な言葉や行為が含まれます。
侮辱罪は名誉毀損罪と異なり、具体的な事実を示す必要はなく、侮辱的な言動そのものが処罰の対象となります。
侮辱罪が成立する可能性が高いケース(例)
- SNSや掲示板で特定の人物を「バカな人」「無能な人」などと侮辱する投稿を公然と行った場合
- ネットの掲示板で「〇〇は社会のゴミだと思う」と個人を特定した投稿
名誉毀損罪と侮辱罪の違い▼
- 名誉毀損罪は具体的な事実の摘示が必要、侮辱罪は事実の摘示は必要なし
- 名誉毀損罪のほうが、侮辱罪よりも刑罰が重い
- 名誉毀損罪の方が慰謝料相場も高い
名誉毀損罪・侮辱罪の違いをより詳しく知りたい方は、下記の記事もぜひご覧ください。
名誉毀損と侮辱罪の違いは?成立するケースを詳しく解説名誉毀損・侮辱罪以外に適用される可能性のある法律
名誉毀損罪や侮辱罪と同様に、ネット上の誹謗中傷や悪質な書き込みが対象となる可能性のある法律として、「脅迫罪」や「業務妨害罪」があります。
- 脅迫罪(刑法第222条)
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合に成立する犯罪です。たとえば、「殺す」「家に火をつける」といった発言がこれにあたります。内容が具体的でなくても、受け手に恐怖を与えれば処罰の対象となります。 - 業務妨害罪(刑法第233条・234条)
虚偽の情報を流したり、悪質な書き込みを繰り返すことで、企業や個人の業務を妨げた場合に成立します。たとえば、飲食店のレビューサイトに虚偽の低評価を大量に投稿する行為や、営業電話・メールの執拗な送付も業務妨害にあたる可能性があります。
このように、投稿内容や態様によっては、名誉毀損罪や侮辱罪にとどまらず、脅迫罪や業務妨害罪といった犯罪として扱われる場合もありますので、注意が必要です。
誹謗中傷の過去事例|民事・刑事での違法判断の実例を紹介

ネット上の誹謗中傷がどのように法的に扱われるのかを理解するには、実際の裁判事例を知ることが重要です。
ここでは、誹謗中傷が原因となった民事(損害賠償が認められた事例)と刑事(刑罰が科された事例)のケースを紹介します。
【民事】「殺してやれ」障害者差別の誹謗中傷に60万円の賠償命令(2024年1月)
2024年1月24日、前橋地方裁判所は、匿名掲示板「5ちゃんねる」に投稿された障害者差別的な誹謗中傷に対し、加害者に60万円の損害賠償を命じる民事判決を下しました。
訴えを起こしたのは、難病により介助が必要な前橋市在住の男性(兵藤一晶さん・48歳)です。兵藤さんは、1日24時間の訪問介護を求める訴訟を起こしました。そのことがネット上で取り上げられ、匿名の投稿者が「生かしておく理由が無いなあ、一思いに殺してやれよ」と投稿しました。
こうした悪質な誹謗中傷の投稿に対し、兵藤さんは弁護士に相談のうえ民事訴訟を提起し、最終的に加害者の男性に60万円の支払いが命じられました(請求額は約190万円)。
参考▼
匿名掲示板で「障害者差別のヘイトスピーチ」 投稿者に賠償命じる【刑事】SNSの誹謗中傷で侮辱罪に問われた24歳男性に有罪判決(2023年1月)
SNS上で交通事故遺族の男性を誹謗中傷する投稿を行ったとして、東海地方の24歳のアルバイト男性が「侮辱罪」で起訴され、拘留29日の有罪判決(刑事処分)を受けました。
投稿の対象となったのは、都内で発生した重大な交通事故で家族を失い、事故防止を訴えていた被害者男性。
投稿内容には「金や反響目当てにしか見えない」「天国の家族が喜ぶとでも?」といった文言が含まれていました。
被害者は投稿を問題視し、弁護士などに相談したうえで、侮辱罪での対応を進めたとみられます。
当初、裁判では無罪を主張していた被告男性でしたが、拘置所で反省し、虚偽の主張を後悔したと語っています。
背景には「SNSで注目されたい」「いいねが欲しい」といった承認欲求があり、誹謗中傷を含む攻撃的な投稿を繰り返すうちにエスカレートしていった経緯が明らかにされました。
参考▼
「いいね」欲しさにSNSで中傷、有罪判決を受けた24歳男性【民事・刑事】ヤフコメの誹謗中傷で損害賠償と罰金命令(2021年5月)
Yahoo!ニュースのコメント欄に、事実無根の内容を投稿して市議を誹謗中傷したとして、大阪府に住む30代の介護士の男性が「名誉毀損罪」で略式起訴され、罰金10万円の刑事処分を受けました。
投稿内容は、「幸運を呼ぶ痰壺みたいなのを買わされそうになった」など虚偽の記述を含み、政治活動への影響も懸念されるものでした。
被害者は弁護士に相談のうえ、Yahoo!に発信者情報の開示を請求。拒否されたため裁判所に申し立てを行い、開示命令が出されました。
その後、損害賠償を求めて民事訴訟を起こし和解に至ったうえで、名誉毀損罪で刑事告訴。略式起訴による処罰が確定しました。
参考▼
<独自>ヤフーニュースに中傷コメント投稿 男性に罰金今回ご紹介したもの以外にも、SNSやネット上での誹謗中傷が原因となった裁判例は数多くあります。
さらに詳しい誹謗中傷の事例を知りたい方は、以下のページもぜひ参考にしてください。
もしネットやSNSで誹謗中傷されたら?できる対応策

ネット上で誹謗中傷の被害に遭ったとき、「どう対応すればいいのか分からない」と感じる方は少なくありません。
誹謗中傷を受けた際に感情的になってやり返してしまうと、さらにトラブルが悪化するおそれもあります。ここでは、誹謗中傷による被害を最小限に抑え、適切に対処するための方法を紹介します。
誹謗中傷の証拠を保存する
誹謗中傷の投稿やメッセージを見つけたら、すぐに削除依頼を出す前に証拠を確保しましょう。
誹謗中傷の内容が記載されたスクリーンショット(投稿日時・投稿者・内容が確認できるもの)や該当URLの記録が、弁護士や警察に相談する際に重要な役割を果たします。
特に、発信者情報開示請求などの法的措置を検討する場合、誹謗中傷の証拠の有無が結果を大きく左右します。
警察に告訴する
「告訴」とは、犯罪の被害を受けた本人が、捜査機関に対して被害の内容を伝え加害者への処罰を求める正式な手続きです。
法的に事件化するためには、被害者からの告訴が不可欠である点を理解しておく必要があります。
誹謗中傷の書き込みが悪質で、加害者に反省の様子も見られない場合、被害者は名誉毀損罪として警察に告訴することが可能です。
名誉毀損罪は親告罪に該当するため、被害者自身が警察などの捜査機関に告訴を行わなければ、原則として捜査は開始されません。
告訴を行うには、誹謗中傷の証拠(投稿のスクリーンショットやURLなど)を揃えた上で、被害届または告訴状を提出する必要があります。
「この誹謗中傷は犯罪にあたるのか?」「本当に告訴できるのか?」と迷った場合には、早めの相談が、被害の拡大を防ぐ第一歩です。
対応には時間がかかることもありますが、加害者が特定され、刑事処分(書類送検・罰金・懲役など)につながるケースもあります。
弁護士に相談する
誹謗中傷の内容が悪質であったり、投稿者が匿名で特定できない場合は、早急に弁護士に相談することが有効です。
弁護士は、誹謗中傷を含む投稿内容が法的に問題があるかどうかどうかを判断し、発信者情報開示請求や損害賠償請求などの手続きを法的な観点からサポートしてくれます。
また、刑事告訴を検討する際も、告訴状の作成や警察とのやり取りについて相談しながら進められるため安心です。
誹謗中傷の被害は、自分ひとりで抱え込みがちですが、専門家に相談することで被害の拡大を防ぎ、迅速な解決が期待できます。
まとめ
SNSやネット掲示板での発言や書き込みは、気軽にできる一方で、名誉毀損罪や侮辱罪といった法的リスクを伴うことがあります。
誹謗中傷が違法となるかどうかは、以下のような要件が判断基準となります。
- 投稿が対象者の社会的評価を下げる内容か
- 不特定多数に見られる状態で発信されたか(公然性)
- 内容が真実でも公共性や公益性がなければ違法とされる可能性がある
特にSNSでは、感情的な投稿や不用意な言葉が拡散されやすく、発信者の意図に関係なく、誹謗中傷とみなされて名誉毀損罪や侮辱罪に問われるケースもあります。
万が一、誹謗中傷の被害に遭った場合や、自分の発言が違法にあたるのではと不安に感じた場合には、早めに弁護士などの専門家に相談することが重要です。
発信者も受け手も誹謗中傷のトラブルに巻き込まれないために、法的な基準やリスクを理解し、冷静で責任ある言動を心がけましょう。