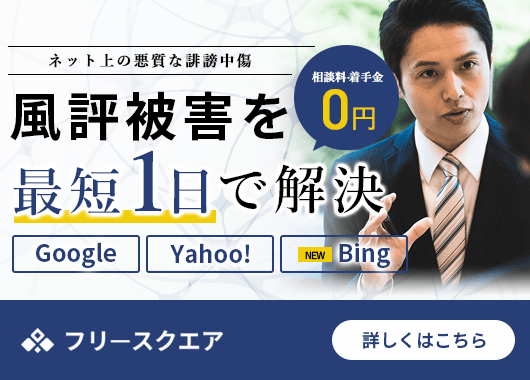現代社会において、企業の評判は一瞬で崩れ去ることがあります。特にインターネットとSNSの普及により、事実無根の噂や誤情報が原因で生じる風評被害は、企業にとって避けがたいリスクとなっています。このような状況下で、企業が直面するリスクを最小限に抑えるためには風評被害対策が必須です。
しかし、「風評被害対策をどのように進めればよいのか?」や「風評被害に対処しなかった場合、どのような影響が出るのか?」という疑問を持つ方は多いでしょう。特に、社会的な信用を重視する企業にとって、風評被害対策の重要性は計り知れません。
本記事では、実際の事例を紹介しながら、風評被害が発生した時の企業の対策方法について詳しく解説します。
風評被害とは

風評被害とは、根拠のない噂や誤解、誤った情報が広まることによって、個人や企業、商品、地域などの評判が不当に傷つけられる現象です。特にインターネットやSNSの普及により、たとえ間違った情報であっても、すぐ広範囲に拡散しやすくなっているため、風評被害の発生とその影響は一層深刻化しています。
さらに、競合他社や個人の恨みなどにより、意図的に悪意のある情報が拡散されることもあります。
風評被害対策とは
風評被害対策とは、誤解や事実無根の噂が原因で企業や個人の評判が不当に損害を受けるのを防ぐために行われる一連の対策のことを言います。
一度拡散された誤った情報は、たとえ事実無根であっても、元の状態に戻すことが困難で、長期間にわたって、悪影響を与え続ける可能性があります。
そのため、風評被害が発生した際は、誤った情報を訂正し、正確な情報を迅速に提供することが不可欠です。また、事実に基づかない噂や誤情報が拡散される前に事前の予防策を講じることも重要です。
企業が風評被害を受けた時の影響

風評被害は企業に甚大な影響を及ぼす可能性があります。根拠のない噂や誤情報が広まることで、企業のイメージが突如として損害を受けることも少なくありません。企業が風評被害を受けた場合、その影響は多方面に及びます。ブランドの信頼性が低下することから始まり、売上の低下、株価の急落、そして採用活動に対するネガティブな影響まで、会社の基盤そのものが揺らぐことになりかねません。
以下で、企業が風評被害を受けた時の影響について解説します。
ブランドの信頼が損なわれる
企業が風評被害を受けた際に生じる影響の一つがブランドの信頼損失です。ブランドの評判は長年にわたる努力と顧客との関係構築によって築かれますが、間違った情報や不当な批判が広まることで、その信頼は一瞬にして揺らぎます。
ブランドの信頼性が損なわれると、新規顧客の獲得が困難になるだけでなく、既存の顧客を失うリスクも高まります。
一度失われたブランドの信頼を取り戻すには、多大な時間と労力を要します。
風評被害が発生すると、ブランドの信頼損失は短期的な売上減少に留まらず、長期的な成長や発展に対しても重大な脅威となる可能性があるのです。
売上の低下につながる
風評被害が発生すると、その最も顕著な影響は売上の低下です。たとえば、ある会社の製品が安全でないとの噂が広がると、消費者はその製品の購入をためらうようになります。リスクを避けるために競合他社の製品を選ぶことが多くなるでしょう。
また、風評被害により会社の評判が損なわれると、商品やサービスへの興味や信頼が薄れます。これが原因で、新規顧客や既存顧客からの問い合わせが減少し、結果的に被害を受けた会社の売上が低下するのです。
株価の下落を引き起こす
風評被害により、誤情報や悪意ある情報が公に拡散されることで、投資家の信頼が損なわれ、市場における企業への評価が低下することがあります。株価は企業の将来性や利益予測に基づいて投資家によって評価されるため、評判が落ちると、その企業の業績が将来悪化するとの懸念が投資家の間で広がってしまうのです。その結果、株価の急激な下落を招くことになります。
株価が下落すると、資金調達や事業展開にも影響を及ぼす可能性があります。特に、公開企業の場合、株価の低迷は会社の公的な評価に直結し、会社の信用度や取引条件に悪影響を与えることが多いです。
採用活動への悪影響
企業が風評被害を受けると、その影響は広範囲に及びますが、採用活動にも悪影響を及ぼすこともあります。
例えば、根拠のない噂によって「ブラック企業」とのレッテルが貼られた場合、求職者の応募数が減少してしまうなどの問題が発生します。現代の労働市場では既に人材不足が問題となっており、風評被害による企業イメージの損失は、この状況をさらに悪化させ、有能な人材の確保を一層困難にさせてしまうのです。
さらに、風評被害は従業員の心理状態にも影響を及ぼし、社内の士気低下を招くことがあります。企業に対するネガティブなイメージが内部にも広がることで、従業員の仕事に対する満足度が下がり、離職率の増加につながる可能性があります。
企業の風評被害の事例紹介
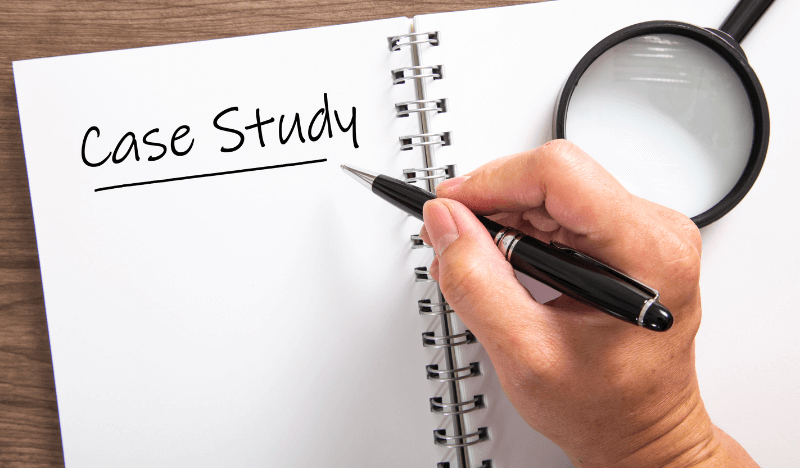
風評被害は様々な形で発生し、しばしば深刻な影響を及ぼします。この章では、風評被害の事例を紹介し、企業が直面するリスクとその影響について詳しく解説します。
風評被害の事例▼
- パンデミックを連想させる名称を持つ商品の風評被害
- ある会社に対して根拠のないブラック企業の噂が広まる
- 倒産情報のデマに関する風評被害
パンデミックを連想させる名称を持つ商品の風評被害
パンデミックが発生すると、その名称が社名やブランド名に含まれる商品が無関係にもかかわらず風評被害に苦しむことがあります。例えば、新型コロナウイルスの流行以降、名前に「コロナ」と含む企業や商品に対する誤解が広まりました。
この影響を受けたのは、新潟県に本社を置く「株式会社コロナ」や、メキシコ産の有名な「コロナビール」です。この企業は、新聞広告やマスコミを通じて誤解を解く努力をしました。
ある会社に対して根拠のないブラック企業の噂が広まる
企業に対する風評被害の一例として、根拠のない「ブラック企業」とのレッテルが付けられるケースがあります。転職の口コミサイトやSNSでは、従業員による会社に対する投稿が自由に書き込まれることが多く、企業の評判に大きな影響を与えます。
実際の事例として、問題を起こして退職した元従業員が事実無根の情報や実際の出来事を誇張して投稿することがあり、その情報が拡散されたことで、「ブラック企業」というレッテルが貼られることが起きています。書き込まれた内容が事実でない場合でも、それを証明するのは困難です。
一度広がった誤解を解くためには、企業が公式な声明を発表するなど速やかな対応が求められます。ネガティブな情報が残り続けると、優秀な人材の採用が難しくなったり、既存の従業員のモチベーション低下や離職率の増加につながるリスクがあります。
倒産情報のデマに関する風評被害
企業が倒産するというデマや噂も、風評被害による一例として挙げられます。
例えば、ある個人が「銀行が潰れる」という未確認の情報をメールで友人に伝え、この情報が速やかに拡散されました。その結果、不安を感じた多くの顧客が銀行に殺到し、数百億円の預金が引き出される事態に発展しました。
この問題に対処するために、銀行は記者会見を開催して噂を否定し、財務支局も同様にデマであるとのコメントを発表しました。これらの公式の対応により、顧客の不安が徐々に解消され、最終的には事態が収束に向かいました。
倒産情報に関するデマや噂のインパクトは非常に大きく、一度広まると瞬く間に多くの人々の間で不安が拡散し、銀行のような金融機関にとっては特に深刻な結果を招きます。
風評被害の事例についてもっと知りたい方は、下記の記事もご覧ください。
風評被害対策:予防編

風評被害は、誤情報やデマが原因で企業や個人に与える影響が非常に深刻です。SNSやインターネット上に一度拡散された情報は簡単には消えないため、速やかな対応が必要です。
風評被害を未然に防ぐためには、予防策を講じることが極めて重要です。ここでは、風評被害の予防施策について詳しく説明します。
自社に関する情報を定期的にチェック
インターネットでは日々無数の情報が流れており、自社の評判を守るためには、SNS、掲示板、ニュースサイト、転職の口コミサイト、情報まとめサイトなど、自社に関連する情報を定期的にチェックすることが重要です。
自社に関する潜在的なネガティブな情報をインターネット上で広がる前に早期に発見することで、風評被害を拡大することなく、最小限の被害で問題を収束させることができます。
最近では、インターネット上で自社の評判を自動的に監視するツールが登場しています。
Yahoo!やGoogleの検索サジェストや関連ワード、さらには各種SNSを24時間自動で監視し、自社のブランドイメージが低下するリスクを未然に防ぐ手助けをしてくれます。このようなツールを活用することで、インターネット上の潜在的な問題に迅速に対応できます。
SNSガイドラインを作成
風評被害の一因としてSNSが挙げられることから、企業はSNSの適切な使用について明確なガイドラインを持つことが重要です。自社の従業員が私生活を含めてどのようにSNSを利用すべきかを示し、企業の公式SNSアカウントの運用において遵守すべきルールを定めた運用ガイドラインの策定を行います。
また、自社のガイドラインを定めるだけではなく、定期的にSNSの利用に関する教育を行うことで、策定したルールの理解と遵守を促進し、風評被害のリスクを低減できるでしょう。
風評被害が起きた時の対策方法

風評被害が発生した場合、その影響に対する迅速な対応が必要です。
放置すると、インターネット上での情報は瞬く間に拡散し、一度広がったネガティブな情報をコントロールすることが困難になります。
しかし、適切な対策を講じることで、風評被害の悪影響を最小限に抑え、企業の信頼と評価を維持することが可能です。
以下で詳しく紹介します。
自分で削除依頼
インターネット上で自社に関する根拠のないネガティブな情報を見つけた場合、ネット上の記事の削除は自分自身で行うことができます。サイト内に設置されている問い合わせフォームや、SNSで直接連絡することで、申請することができます。削除依頼を行う際には、対象となるサイトやSNSの利用規約を事前に確認し、その手順に従って行うことが重要です。
しかし、依頼したすべての投稿が削除対象となるわけではありません。たとえば、自社に関する間違った情報であっても、その内容がサイトの規約に違反していない場合、削除されない可能性があります。そのため、削除依頼を行う前には、自分のケースが規約のどの条項に該当するのかをしっかりと確認した方が良いでしょう。
弁護士に相談
自分でネット上の誤情報を削除できない場合、法的知識を持つ弁護士に依頼をするのが効果的な解決策の一つです。ご自身での対応では、時間がかかることや削除してもらえないケースがあります。弁護士は、法律違反があるかどうかを判断し、適切な法的手続きを通じて迅速に対応することが可能です。
自身で対応が難しい場合は弁護士に相談することが推奨されます
弁護士に依頼するメリット▼
- 時間と労力の節約
- 法的根拠をもとに削除依頼をしてくれる
- 損害賠償請求についても相談できる
専門業者に削除依頼

風評被害が広がると、GoogleやYahoo!の検索サジェストなどの候補に自社に関するネガティブなキーワードが表示されることがあります。
事実無根であっても、自社に関連するネガティブワードがサジェストなどに表示されると、会社や個人のブランドイメージに悪影響を与える可能性が高まります。
専門業者は不適切または事実無根のワードが検索候補に表示された際に削除、または出現しないように予防することが可能です。
GoogleやYahoo!への削除申請や弁護士への相談はハードルが高く感じられることが多いため、サジェストの風評対策では専門業者を利用する企業が多いです。
専門業者の多くは、サジェストの削除だけでなく予防対策にも精通しており、両方の対策ができます。
ネット記事に関しては、誤った情報の記事を抑制するための逆SEO対策を専門とする業者もいます。逆SEOは、ネガティブなコンテンツを検索結果の下位に押し下げることで、目立たなくさせる施策のことです。
企業によって成果が出るまでの時間や成功率が異なるため、風評対策の実績が豊富な業者を選ぶことが重要です。
専門業者を選ぶ際のポイント▼
- 対策費用(月額固定または成果報酬など)
- 成功率(対策会社によって異なるため必ず確認しましょう)
- 契約期間(初回の契約期間や更新後の契約についても確認しましょう)
- 成果の報告(成果の報告方法を確認しましょう)
誤解を解くために公式の声明を出す
風評被害が起きた際、誤解を解くために公式の声明を発表することで、誤情報や不確かな噂が引き起こす混乱を最小限に抑えることが可能です。
例えば、あるSNSでチョコレートの中に虫が入っていたとする投稿が拡散され、企業に風評被害が発生しました。企業は迅速に対応し、「昨年以前の商品であり、購入後に虫が混入した可能性が高い」と推察し、公式SNSで事実関係を説明しました。
その結果、投稿者は事実誤認を認め、投稿を削除。この一連のスムーズな流れは、ネットユーザーからも高く評価され、「広報の鑑だ」「迅速な対応で素晴らしい」といった称賛の声が寄せられました。
ただし、声明を出す前に、事実確認をすることが重要です。誤った情報に基づく声明は、さらなる混乱を招くことになりかねません。
まとめ
風評被害は現代社会において企業が直面する深刻なリスクの一つであり、インターネットとSNSの普及によってその影響はさらに大きくなっています。風評被害に適切に対応するためには、事前の予防措置と迅速な対策が必要です。
風評被害が発生した際の対応策としては、誤解を解くために迅速かつ正確な公式声明を発表すること、不適切なコンテンツの削除依頼を自力または専門業者及び弁護士を通じて行うことが効果的です。
企業の評判は非常に脆く、一度低下すると回復が困難になることが多いため、風評被害対策は非常に重要と言えるでしょう。