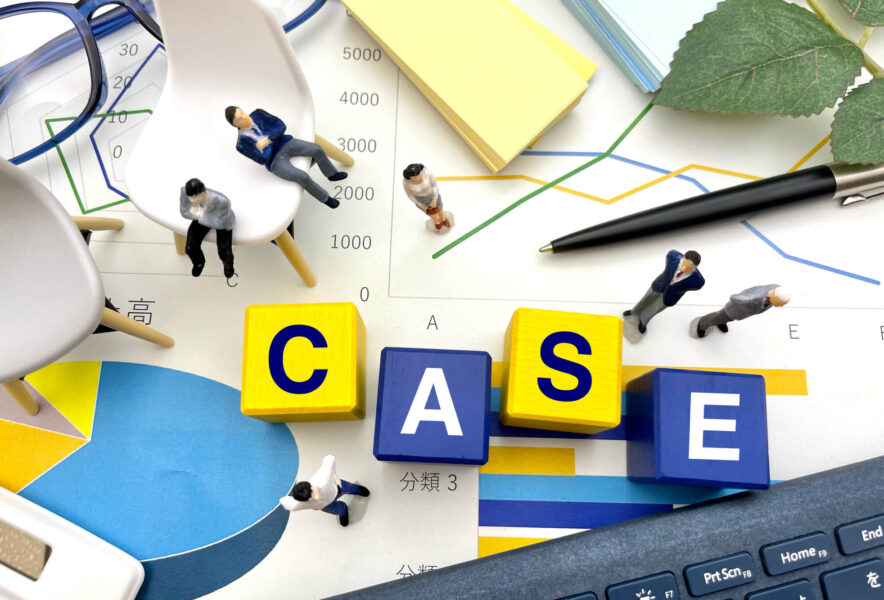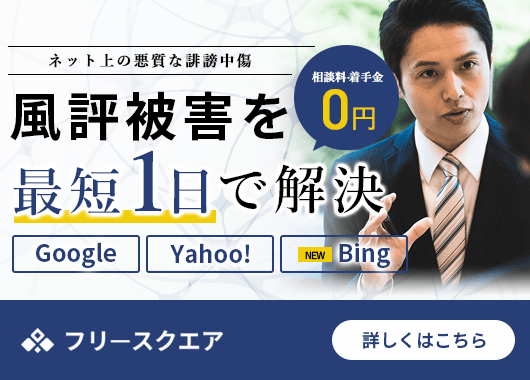ネットやSNSが日常生活に欠かせないツールとなる中で、その匿名性や間違った正義感などが原因でネット上の誹謗中傷が社会問題となっています。
SNSやネットでの無責任な発言が、侮辱罪や名誉毀損につながるケースが後を絶ちません。
このような状況から、被害者が弁護士に相談し、加害者に対して法的措置を取るケースが増加しています。
本記事ではネット上での誹謗中傷で訴えられた事例を紹介し、損害賠償が成立した内容についても掘り下げていきます。
ネットの誹謗中傷とは

ネットの誹謗中傷とは、インターネット上のSNS、掲示板、ブログなどで行われる、特定の個人や企業などに対して、侮辱的な言葉や嫌がらせ、デマ情報、虚偽の発言などを用いて、その名誉や人格を傷つける行動を指します。
特に昨今はSNSやネットの普及により、誹謗中傷が匿名で行われることが一般的になり、その影響は瞬時に拡散されることがあります。
匿名性が保たれる環境では、一部のユーザーが悪用して、憎悪や偏見に基づく攻撃的な内容を投稿することがあります。
誹謗中傷は、相手の社会的評価や感情、名誉に悪影響を与えるものであり、時にはその人の心身の健康に深刻な問題を及ぼすこともあります。
ネットの誹謗中傷で問われる可能性のある代表的な罪

インターネット上での誹謗中傷は、しばしば法的な問題に発展します。
ネット上での誹謗中傷によって問われる可能性のある代表的な罪として、名誉毀損罪と侮辱罪があります。
名誉毀損罪
名誉毀損罪の刑罰は、日本の刑法第230条に基づいて定められています。名誉毀損罪が成立した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
なお、刑事上の名誉毀損罪とは別に、民事上で不法行為が成立する場合には、損害賠償請求の対象となります。
名誉毀損罪が成立する条件
- 具体的な事実の摘示
- 人の名誉を毀損
- 公然性
名誉毀損罪は、「事実」を摘示することにより成立します。「事実」とは、証拠によりその存否を決することのできる事項のことであり、真偽は問いません。つまり、摘示した事実が仮に真実であったとしても名誉毀損罪は成立する可能性があるということです。
なお、民事上の名誉毀損の場合には、事実を含まない意見・論評のような表現であっても不法行為となる場合があります。
名誉毀損罪における名誉とは、その人に対する社会的な評価のことです。したがって「名誉を毀損」 とは、その人に対する社会的な評価や評判を落とすことです。なお、ここでいう「人」は生身の人間に限られず、会社等の法人も含まれます。
また、「公然」とは、不特定又は多数の人が知り得る状況を意味します。SNSへの投稿などが典型例です。
これらの条件が全て満たされる場合、名誉毀損罪が成立することになります。
例えば、SNSで他人の犯罪歴を投稿したり、ある企業の製品を指して不良品であるというデマ情報広げることは、名誉毀損罪に該当する可能性が高いです。
名誉毀損罪が成立しない場合
- 公共の利害に関する事実に係ること(公共性)
- 専ら公益を図る目的に出たこと(公益目的)
- 摘示された事実が真実であると証明されること(真実性)
例えば、政治家の汚職を告発するような場合など、公表することに社会的な意義のあるものについて認められる可能性があります。
侮辱罪
侮辱罪についてネットの誹謗中傷で訴えられた事例

ネット上の誹謗中傷によって実際に訴訟に発展した事例を紹介します。
ここで取り上げる事例には、名誉毀損が成立したものや損害賠償が認められたものも含まれています。
週刊誌と週刊誌ネット記事による名誉毀損で損害賠償請求が認められた事例(平成31年3月5日判決言渡し)
茨城県守谷市の市長は、週刊誌「FRIDAY」とネットの「FRIDAYデジタル」に掲載された記事が自身の名誉を毀損したとして損害賠償を請求しました。
記事には「茨城守谷市長の『黒すぎる市政』に地方自治法違反疑惑」という見出しがつけられており、市政運営における疑惑が指摘されていました。
公人(政治家などの公的な役職にある人物)に対する報道は、社会的な利益があるため、報じられた内容が事実であれば名誉毀損には該当しません。そのため、記事内容の真実性がこの判決の決定的な要素となりました。
結果的に、この裁判では、週刊誌側が記事内容の事実性を証明できなかったため、名誉毀損が成立し、市長への慰謝料として150万円、さらに弁護士費用として15万円の支払いが命じられました。
判決
☑慰謝料:150万円
☑弁護士費用:15万円
ネットのなりすましと誹謗中傷:130万円の損害賠償命令がくだされた事例(2017年8月)
この栽判例は、ネット上の匿名性を利用したなりすましによる名誉権、プライバシー権、肖像権、そしてアイデンティティ権の侵害に関するものです。
原告は、被告が原告になりすましてネット掲示板に不適切な内容の投稿したことにより、名誉権,プライバシ ー権,肖像権及びアイデンティティ権を侵害されたとして、不法行為に基づき、慰謝料や弁護士費用を含む合計723万6000円の損害賠償を請求しました。
被告はなりすまし自体を否定したものの、裁判の結果、名誉権と肖像権の侵害が認められ、慰謝料などを含め130万6000円の支払いが被告に命じられました。
判決のまとめ▼
名誉権の侵害:〇
被告がなりすまし、公然と原告が行ったかのように見せかけた投稿をネット掲示板に投稿し、原告の社会的評価を低下させたため、名誉権侵害があったと判断されました。
肖像権の侵害:〇
プライバシー権及び肖像権の侵害: 被告が原告の顔写真をプロフィール画像として使用し、原告の許可なく公開したため、肖像権の侵害が認められました。
プライバシー権:×
原告が自ら公開した写真であったため認められませんでした。
アイデンティティ権の侵害:×
被告のなりすましがアイデンティティ権を侵害したとは認められず、この部分は棄却されました。
イラストの無断転載と誹謗中傷の事例(2013年7月)
この裁判では、漫画家であるB氏は、被告がB氏の描いた似顔絵を無断で画像投稿サイトに掲載したことが著作権及び著作者人格権の侵害、また、その削除を求めた際に被告がSNSにB氏から殺害予告を受けたかのような内容を投稿したことが名誉毀損にあたるとして、不法行為に基づき、400万円の損害賠償を請求しました。
裁判所は、被告がB氏が描いた似顔絵を無断で画像投稿サイトに投稿したことはB氏の著作権(公衆送信権)を侵害したと認定し、また、その方法がB氏の名誉又は声望を害する方法であったとして、著作者人格権も侵害したと判断しました。
さらに、被告が殺害予告をしたとの事実を摘示することで、B氏の社会的評価を低下させたとして名誉毀損も認められました。
ただし、被告は原告の要請を受けた後に本件似顔絵の写真を速やかに削除しており、閲覧者も多数に及んでいなかったとして、結果的には、被告に対して50万円の損害賠償が命じられるに留まりました。
損害賠償の内訳▼
・著作権侵害に対する損害賠償:
被告がB氏の描いた似顔絵を無断でインターネット上に掲載したことが著作権を侵害した行為として、20万円の損害賠償が認定されました。
・著作者人格権の侵害に対する損害賠償:
被告がB氏の似顔絵を無断で公開し、名誉又は声望を害する方法で著作物を利用した行為が著作者人格権を侵害したとして、15万円の請求が命じられました。
・名誉毀損に対する損害賠償:
被告の不適切なツイートによりB氏の社会的評価を低下させた行為が名誉毀損として、15万円の請求が命じられました。
池袋暴走事故の遺族にSNSで誹謗中傷した男に有罪判決(2023年1月)
東京地裁は、池袋暴走事故の遺族をSNS上で誹謗中傷した無職の男性に対して、侮辱罪で拘留29日の判決を言い渡しました。
被告人は、遺族のSNS投稿に対して不適切な内容のコメントをし、「金や反響目当て」「男は新しい女作ってやり直せばいい」と非難しました。裁判では、この投稿が遺族の社会的評価を一方的に下げたものと判断しました。
被告人は投稿の意図について侮辱する意図はなかったと主張しましたが、裁判では投稿内容から侮辱の意図があったと認定しました。
被告人はまた、他の刑事事件にも関与しており、その罪については懲役1年、執行猶予5年の判決が下されました。
遺族は判決後、判決に満足しており、被告人に対して今後言葉による傷害を避けるよう希望を表明しました。
事件とは無関係の方が誹謗中傷され名誉毀損が認められた事例(2022年3月)
事件の背景として、神奈川県の東名高速道路で発生したあおり運転による死傷事故に関連し、原告A氏と同姓の男性が危険運転致死傷罪等で逮捕されました。
A氏自身はこの事故とは無関係でしたが、ネット上では、A氏とA氏が代表を務める会社が事故に関与しているかのように虚偽の情報が拡散されました。
A氏とA氏の会社は、このような虚偽の情報を投稿した行為が名誉毀損に当たるとして、複数の被告に対して、不法行為に基づき損害賠償を請求しました。
結果的には、被告Cには22万円、被告D、E、F、Gにはそれぞれ16万5000円の損害賠償が命じられました。
侮辱罪で略式起訴された事例(2021年4月)
恋愛リアリティー番組「テラスハウス」に出演していたプロレスラーの女性は、ネット上で激しい中傷にさらされました。
他の出演者に怒る場面が映された後、彼女のSNSには生命を否定するような書き込みが増加しました。その結果、遺書のようなメモを残して自ら命を絶ちました。
この悲劇に対して、警視庁は彼女に対する中傷投稿を調査し、特に悪質な約30件の投稿をした10アカウントを特定しました。その中の一人、福井県の30代男性が侮辱容疑で書類送検され、彼は投稿行為を認めました。
これまでに、この男性を含めて少なくとも2人が侮辱罪で書類送検されており、別の加害者は科料として9千円を納付したことが報告されています。
企業が誹謗中傷され、投稿者に損害賠償請求をした事例(2024年12月)
あるファッション通販サイトを運営する企業が、ネット上で繰り返された誹謗中傷投稿に対して法的措置を取りました。この企業は、特にオンライン掲示板での悪意あるコメントに対応するため、法的手続きに従い発信者情報の開示を裁判所に申し立てました。
開示請求が認められた結果、特定の誹謗中傷投稿者に対して損害賠償請求訴訟を提起するに至りました。
和歌山県と滋賀県に住む二人の投稿者が特定され、彼らに対する訴訟が進行中です。さらに、他の複数の発信者に対しても同様の手続きが進行しています。
誹謗中傷で逮捕・訴えられた加害者はどうなるの?

ネット上での誹謗中傷は、誰もが意図せずに加害者になるリスクを持ちます。
誹謗中傷で逮捕や訴訟に至った場合、加害者が直面するリスクについてどのようなものがあるのでしょうか?
以下で詳しく解説します。
損害賠償を請求をされる
誹謗中傷で逮捕・訴えられた加害者には、損害賠償を請求される可能性があります。
この場合、被害者は弁護士を通じて、加害者に対して、名誉毀損などによる損害や精神的苦痛について賠償を求めることが一般的です。
賠償金の請求額は、誹謗中傷の内容や影響範囲、被害者の受けた実際の損害に基づいて決定されることが多いです。
また、訴訟過程で発生する弁護士費用も、加害者が支払う必要がある場合があります。
前科がつく可能性がある
誹謗中傷が原因で有罪判決を受けると、前科が記録されます。被害者との間で弁護士の助けを借りて謝罪や示談が成立すると、不起訴や執行猶予を得られることもありますが、犯罪の重さや反省の度合いによっては実刑を言い渡されることもあります。 特に、誹謗中傷が激しい場合や繰り返し行われている場合には、罰金刑や懲役刑が科されることもあります。
前科がつくと、将来にわたって社会生活や就職に影響を及ぼすことになるでしょう。
会社を解雇される
誹謗中傷のために有罪と判定されれば、職を失うリスクが高まります。
会社側から見れば、特に公に知られた場合、社員の犯罪行為は組織の評判に悪影響を及ぼすと見なされます。そのため、企業はブランドのイメージを守るため、またその他の従業員や顧客との関係を守るために、問題のある従業員との雇用関係を解消することを選ぶことが多いです。
会社の就業規則や雇用契約を参考にして、弁護士と相談の上で裁判の結果に基づいて処分が決定されることが多いです。
まとめ
ネットやSNSが生活に欠かせないものとなる中で、その匿名性や誤解を招く情報が原因でネット上の誹謗中傷が大きな社会問題となっています。
昨今は被害者が加害者に対して法的措置を取るケースが増加しており、特に誹謗中傷による名誉毀損罪や侮辱罪が問題となることがあります。また、加害者に対して損害賠償を請求する訴訟が起こされる場合もあります。
ユーザーは自身の発言がもたらす影響を常に意識し、責任を持って発言することが求められるでしょう。
もし、ネット上で自分に対する誹謗中傷の投稿を発見した場合は、一人で抱え込まず、速やかにネットの誹謗中傷対策に強い弁護士に相談することを推奨します。弁護士の助けを借りることで、適切な対応を行い、法的な権利を守ることが可能です。
また、弁護士は、誹謗中傷に関する損害賠償請求やその他の法的対応もサポートしてくれます。