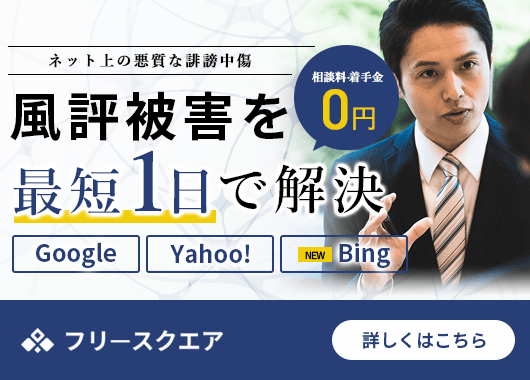風評被害は、根拠のない噂、誤った情報が広がることによって、企業や個人の信頼が不当に損なわれる現象のことを言います。
ネットやSNSの普及により、一度広がった間違った情報や不正確な噂は瞬く間に拡散し、企業の評判に甚大な影響を与えることがあります。
本記事では、さまざまな風評被害の事例をお伝えし、企業が直面するリスクと風評被害の対策について解説します。
企業の具体的な風評被害の事例を紹介
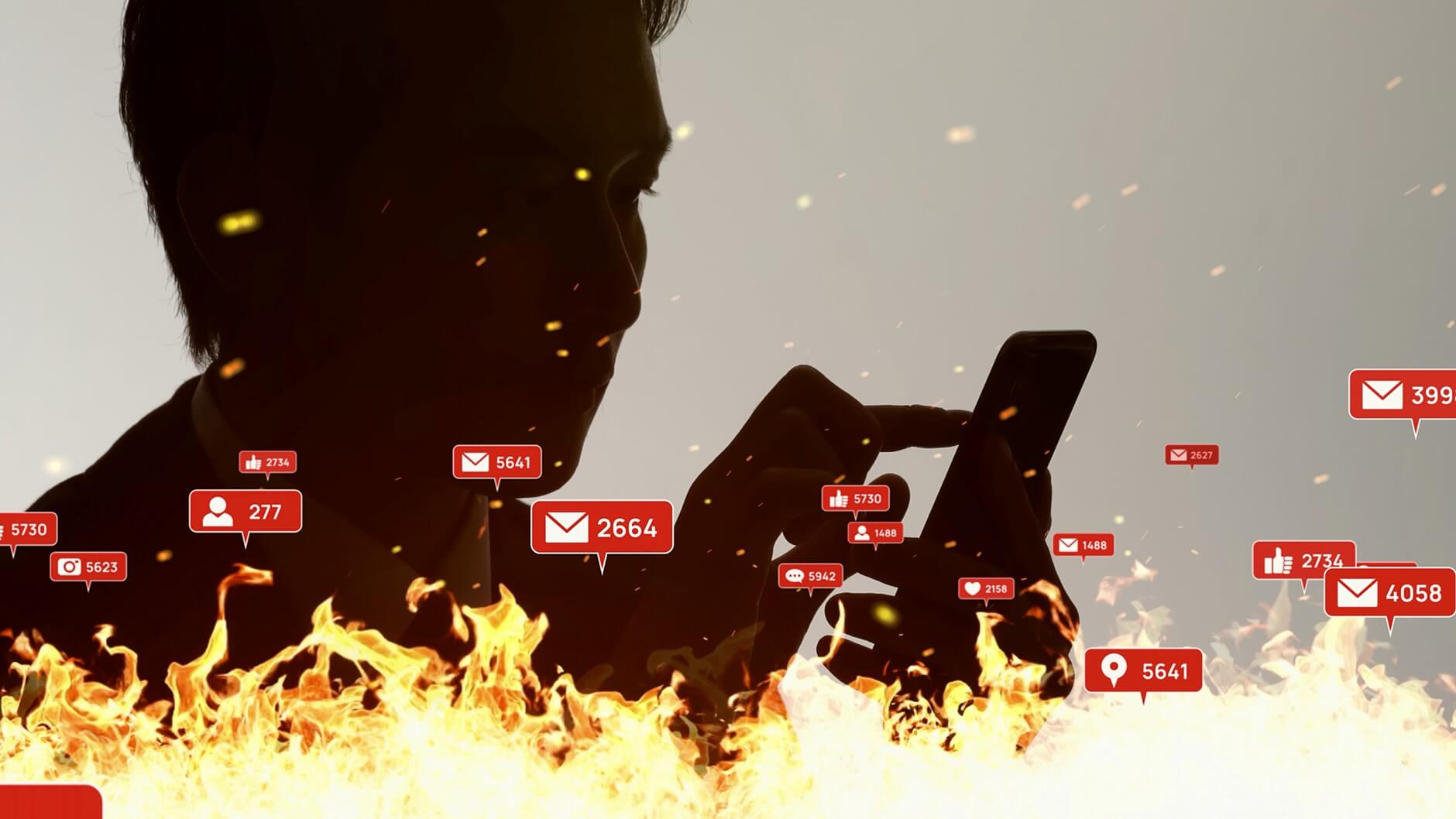
ネットやSNSが広く普及した現代において、デマや誤解が原因で企業が風評被害を受けるケースが増えています。ここでは企業の風評被害の事例を紹介します。
風評被害にあった企業がどのような対応や対策を行ったのかも確認してみましょう。
チョコレートの虫混入疑惑で風評被害を受けた企業の事例
人気チョコレートブランドの商品から虫が出てきたとする投稿がSNSで拡散されました。
この投稿によって、企業の信用に疑問が投げかけられる事態となりましたが、企業のSNS公式アカウントで速やかに対応し、該当の商品が毎年発売される季節商品であること、そして今年の発売がまだ2週間後からであるため、昨年以前に発売された商品である可能性が高いと説明。
投稿者は事実誤認であったとして投稿を削除し、企業側は一連の経緯をSNSで公開しています。
この企業の迅速な対応は、ネットのユーザーから大きな称賛を受けました。特に、食品業界での異物混入はデリケートな問題であり、実際の事実に関わらず企業イメージのダウンリスクが高い中、この企業の透明性と速やかな対応はさらにブランド価値を高めたと言えるでしょう。
福島県産牛肉の風評被害の事例
福島第一原発事故に伴う風評被害が仙台市内の牛タン店に深刻な影響を与えました。この企業が運営する牛タン店では、外国産の肉を使用しているにもかかわらず、「仙台名産」というイメージから観光客が国産と誤認し、消費をためらったことが主な原因です。
この誤解による収益激減を受けて、企業は東京電力に約1900万円の損害賠償を請求し、最終的に政府の原子力損害賠償紛争解決センターを通じて約1300万円の支払いで和解が成立しました。
「ブラック企業」とレッテルが貼られた風評被害の事例
たとえ実際に違法行為があったわけではなくても、一度ブラック企業とのレッテルが貼られると、その影響は甚大です。例えば、ある大手飲食チェーンは業績予想の大幅な下方修正を発表しました。また、別の有名な居酒屋チェーンは数多くの店舗を閉鎖することになりました。
これらの企業では共通して、ブラック企業とのイメージが定着したことで、人材の確保が困難になり、結果として業績をさらに悪化させる要因となっています。
最近では、SNSやネットなどで従業員が企業名を記載した上で職場の愚痴や悪口を書き込み、その情報が拡散されることが多いです。事実無根であっても、拡散された情報がブラック企業のレッテルをもたらすケースが増えています。
ブラック企業の風評被害が発生すると、そのダメージはしばしば取り返しのつかないものになります。
風評被害により収益が低迷した企業の事例
北海道の蘭越町では、地熱資源調査中に水蒸気噴出事故が発生し、一時的に高濃度ヒ素を含む水が流出しました。この事件が報じられたことにより、町が風評被害を受け、特に農産物の販売に大きな影響を与えたのです。
水蒸気噴出事故の発生の影響で、地元農家は例年通りの注文が入らない状況となり、収益に大きな打撃を受けました。
町では事故後、迅速に取水停止措置を行い、安全が確認されるまでの間、川からの取水を中止しました。さらに、地元の大学の専門家によれば、栽培される農作物は安全であるとの見解が示されましたが、地元農産物への不安は払拭されず、多くの農家が経済的な困難に直面しています。
地元の行政は、水質の安全性を毎日測定し公表することで、消費者の信頼を取り戻す対策を実施しています。また、町はホームページを通じて安全性の情報を積極的に発信し、地元製品の支援を呼びかけています。
このように安全が確認された後も風評被害の影響は長期にわたり続くことがあるのです。
大手製薬業界の同名企業への誤った風評被害
ある地方の大手原薬メーカーが、解熱鎮痛剤の製造過程で、安価な成分を無届けで混入し、出荷していた事件が発覚しました。この件は法令違反が疑われ、地方当局による厳しい業務停止命令が下されたのです。この原薬メーカーの不祥事は、全国的に報じられ、広範な影響を及ぼしました。
同時に、全く関係のない大阪に本拠を置く同名の企業が風評被害を受けました。この企業は競泳用水着やその他の水着関連製品を製造しており、この事件とは一切関連がありませんでしたが、名前が同じであるために、一部の消費者とメディアからの誤解が生じ、無関係な企業にも苦情や批判が殺到しました。
事態の収束を図るため、同名の企業は積極的に消費者やメディアに正しい情報を提供しました。
この事例では企業名が一致するだけで、全く関係のない企業までも風評被害に巻き込まれる可能性があることを示しています。
全く無関係な企業に対して風評被害が発生した事例
2017年、神奈川県の東名高速道路で発生した悲劇的なあおり運転事故が、全く無関係な企業に対する誤った風評被害を引き起こしました。事故により夫婦が死亡し、その後、容疑者と全く無関係の北九州市の企業の社長がネットで容疑者の「父親」と誤認されました。
社長の名前や企業情報がネットで拡散され、彼とその会社は重大なプライバシーの侵害と嫌がらせを受けました。社長の会社には、一日に100件以上の嫌がらせ電話が寄せられ、彼は子供の安全を守るために学校を休ませるなどの措置を取らざるを得ませんでした。
この事件の影響で、石橋社長は名誉毀損で5人を訴え、福岡地裁は社会的評価を低下させたと認め、被告に対し合計176万円の賠償支払いを命じました。さらに、このうちの4人は名誉毀損罪で罰金30万円の略式命令を受け、1人は正式裁判で罰金30万円の判決が確定しています。
間違った情報が招いた風評被害の事例
1996年、大阪府堺市の学校給食でO157による集団食中毒が発生。この事件では、最初にカイワレ大根が感染源として報じられました。この報道により、カイワレ大根の消費は急激に減少し、多くの生産者が経済的打撃を受け、業界全体が壊滅的な影響を受ける事態に至りました。
しかし、その後の詳しい調査で、実際の感染源はカイワレ大根ではないことが判明したのです。風評被害を受けたカイワレ大根の農家は、国に対して損害賠償を求め、裁判で勝訴しました。
新型コロナウイルスによる風評被害
新型コロナウイルス感染拡大初期、横浜中華街は重大な風評被害に見舞われました。中国・武漢での感染拡大後、日本で初めて確認された患者が「神奈川の中国人男性」と報じられたことから、中華街が感染の中心地であるかのような誤解が拡散されました。
この情報はSNSを通じて拡散され、横浜港に停泊中のクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」での集団感染事案がさらにそのイメージを悪化させました。
政府の自粛要請により、来街者が激減し、中華街の売り上げは最盛期の約10分の1まで落ち込んだと報じられます。さらに、複数の店舗には中国人への誹謗中傷を含むヘイト手紙が届けられました。
企業が直面する風評被害がもたらすリスク

風評被害が企業に与えるリスクは多岐にわたります。
風評被害が企業に与えるリスク▼
- ブランドイメージの低下
- 売上の低下
- 人材の流出および採用への悪影響
- 株価の下落
- 事業運営の妨げ
まず最も顕著なのが、ブランドイメージの低下です。一度損なわれた信頼を回復するには、長期間にわたる努力とコストが必要となり、これが直接的に売上の低下に繋がります。消費者の信頼が失われると、その影響は直接的に売上の低下に繋がり、企業の財務状況を圧迫します。
さらに、風評被害は採用活動にも悪影響を及ぼします。企業の評判が悪化すると、優秀な人材が応募をためらう原因となり、人材の質の低下や採用コストの増加につながることがあります。
風評被害は株価に影響を与える場合があります。投資家が企業の将来性を見極める際にブランドの信頼性を重視するため、風評被害によって企業評価が下がる場合、株価の下落が起こりやすくなります。
風評被害対策について詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。
風評被害の事例から学ぶ対策3選

風評被害は企業にとって深刻なリスクをもたらすため、速やかな対応が求められます。
ここで紹介した事例を踏まえ、風評被害が起きた場合は以下の対策を講じると良いでしょう。
風評被害が起きた時の対策▼
- 事実確認と公式声明の発表
- ネットの風評被害は専門業者に相談
- 弁護士に相談
人気チョコレートブランドが虫混入疑惑で風評被害を受けた事例では、迅速な事実確認を行い、公式のSNSアカウントで該当商品が昨年以前に発売された季節商品であり、まだ今年の販売が開始されていないことを投稿。間違った情報を広めた投稿者は事実誤認であることを認め、投稿を削除。企業はその経緯を公開し、透明性を保ちながら問題を解決しました。
このように、風評被害が起きた場合、誤解を解くために事実確認と公式の声明を発表することで、誤情報や不確かな噂が引き起こす混乱を最小限に抑えることができます。
また、ネットで風評被害が広がると、GoogleやYahoo!の検索サジェストなどの候補にネガティブなキーワードが表示されることがあります。例えば、「ブラック企業」という言葉が企業名と一緒に表示されるようになると、その企業に対するネガティブなイメージが企業の評価に深刻な影響を及ぼすことになります。
専門業者は不適切または事実無根のワードが検索候補に表示された際に削除、または出現しないように対策をすることが可能です。
ネットの風評被害に悩んでいる際はまず専門業者に相談すると良いでしょう。
さらに、 風評被害が法的な問題を引き起こす可能性がある場合、弁護士に相談することが望ましいです。法的アドバイスを受けることで、企業は適切な対策を講じることができ、場合によっては法的手続きを通じて名誉回復や損害賠償を求めることができます。
まとめ
事例で紹介された企業の中には、風評被害に速やかに対応し、間違った情報に対して正確な情報を提供することで、評判をほとんど低下させずに見事に対応した例もあります。
しかし、一度企業の評判が落ちると、それが原因で長期的に売り上げが低迷し、最悪の場合には企業が倒産に追い込まれることもあります。
さらに、風評被害が解消された後も、インターネット上にはネガティブな情報が残り続けることがあります。このような状況では、専門業者に相談するか、法的な措置が必要な場合は弁護士に相談することが有効です。
風評被害は企業にとって深刻なリスクをもたらし、その影響は企業の評判や収益に直接的な損害を及ぼす可能性があります。風評被害が発生した際には、迅速な対応が不可欠です。