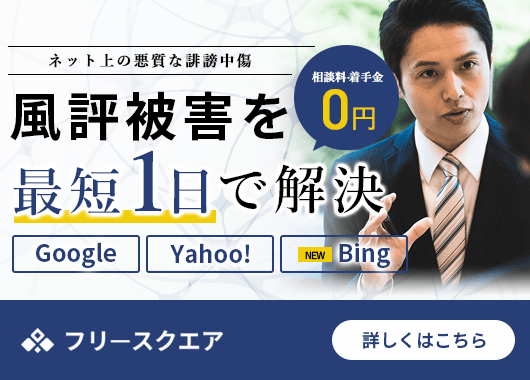採用ブランディングは、企業の認知度を高めるとともに、求職者に対して自社の魅力を伝え、自社に合った人材の入社意欲を高める戦略的なアプローチです。
現在、日本の採用市場は「売り手市場」と呼ばれる状況にあり、多くの企業が人手不足に悩まされています。経営者や人事担当者は、優秀な人材に自社を選んで入社してもらうための方法を模索しています。
採用ブランディングは、これらの課題を克服するために不可欠な要素となっています。
この記事では、採用ブランディングの基本から実際に企業が優秀な人材を獲得するための進め方までを詳しく解説します。
採用ブランディングとは?

採用ブランディングは、企業がターゲットとする求職者に対して自社の魅力を伝え、優秀な人材を引き寄せるための戦略的なアプローチです。これは、企業の認知度を高めるだけでなく、企業のビジョンや働きがい、キャリアの成長機会などを明確にし、求職者に自社を選んでもらうための活動が求められます。
現在の採用活動は、単に多くの応募者を獲得することから、自社に最適な人材を引き寄せる方向へとシフトしています。
企業が求める人材に入社してもらい、長く活躍してもらうためには、他の企業とは異なる独自の特徴を打ち出すことが必要です。そのため、採用プロセス全体で一貫したブランディングを行い、求職者を惹きつける採用コンセプトを定義し、そのコンセプトを正確に伝えることがとても重要です。
また、実際の職場環境や社員の声を活用して、リアルな企業像を構築することも、信頼性の高いブランディングには不可欠です。
そもそもブランディングとは
ブランディングとは、企業や商品の独自性を形成し、そのコンセプトを一貫して市場に伝えるマーケティング戦略です。ここでいう「ブランド」とは、他と区別される独特な特徴やイメージのことを指し、消費者や利用者に対して強い印象を与え、ブランドとしての認識や好意、信頼を築くことが目的です。
通常のブランディングが消費者や顧客をターゲットにしているのに対し、採用ブランディングは求職者をターゲットとし、企業を「働きたい場所」としてアピールすることに焦点を当てています。これらは目的が異なりますが、共にブランドコンセプトを構築して各目的を達成しようとする点で一致しています。
採用ブランディングがなぜ注目されているの?

参照:厚生労働省
現在の採用市場は、少子高齢化による人手不足と労働人口の減少に直面し、企業は高度化する人材要件に応じて、即戦力となる優秀な人材を獲得するための競争が激化しています。厚生労働省の報告によると、日本は今後、本格的な人口減少社会に突入していくことが確認されており、これが労働市場に大きな影響を及ぼすことが予測されます。
従来の採用方法、つまり求人広告や転職エージェントを通じて「転職意欲が高い求職者」を対象とする手法では、限られた人材プールからの採用が難しくなる一方です。
このような売り手市場の環境では、企業が求職者から選ばれるためには、他社とは異なる魅力を持ち、求職者にしっかりと伝える必要があります。採用ブランディングはまさにこの課題に対応する戦略であり、企業文化や働きがい、キャリア成長の機会などを前面に打ち出し、企業が提供する独自の価値を明確に伝えることで、企業のビジョンに共感する人材を引き寄せることができます。
さらに、インターネットやSNSの普及により、企業のイメージや働き方が透明になり、求職者は、より多くの情報に基づいて企業を選ぶようになっています。
そのため、採用ブランディングによる企業の訴求は適切な人材とのマッチングだけでなく、企業全体のブランド価値の向上にも影響を与えるため注目されているのです。
採用ブランディングの目的を解説

採用ブランディングの主な目的は、企業がビジョンや価値を明確に伝えることにより、経営戦略に沿った適切な人材を採用することにあります。近年、事業環境が急速に変化する中で、企業の事業戦略と採用戦略がずれてしまうことがしばしばあります。
採用ブランディングを通じて、企業は事業の方向性に合致した人材を明確にし、自社の価値観やビジョンを整理して発信できます。その結果として、企業と人材のミスマッチを防ぎ、組織にとって最適な人材を確保できるのです。
採用コンセプトが明確であればあるほど、企業の理念が分かりやすくなり、求職者は入社後の職場環境を容易にイメージできます。
採用が難しい時代において、応募者が多くない状況や採用した人材がすぐに退職してしまうことは、企業にとって大きな問題です。自社のビジョンに深く共感する人材は、一般的に職場で長く活躍し、定着率も高い傾向にあります。したがって、採用ブランディングはただ人を集めるだけでなく、長期的に会社で貢献してくれる優秀な人材を確保することが最大の目的と言えるでしょう。
採用ブランディング・採用広報・採用マーケティングの違いは?

採用ブランディングはただ人材を集めるだけではなく、企業の価値観、理念、働きがいといった内面的価値を通じて、企業と求職者との間に深い共感と理解を築き上げることを目指します。
採用広報と採用マーケティングは、共に企業の採用ブランディング戦略を支える重要な役割を担っていますが、目的と手法において異なる点があります。
採用広報の役割
採用広報とは、企業が求める人材を惹きつけるために行う広報活動です。主な目的は、企業のポジティブなイメージや働きがいのある環境を広く知らせることです。企業の知名度や魅力を向上させ、間接的に企業に合った適切な応募者を引き寄せることを目指します。採用ブランディングと混同されがちですが、採用広報は主に企業の現在のイメージや情報を広めることに重点を置きますが、「自社のブランド化」は含まれません。
採用広報は、主にメディアリレーションズ(報道機関との関係構築)、イベントの開催、社内外のニュースリリース、ブログなどを通じて行われます。SNSを通じて求職者とコミュニケーションを取ることもあり、企業が持つカルチャーや価値観を強調し、広く情報を拡散します。
採用マーケティングの役割
採用マーケティングの目的は、ターゲットとなる求職者を引きつけて応募に至らせることです。応募者の増加を目指し、より戦略的な方法で取り組みます。マーケティング手法を用いて、ターゲットとなる候補者に積極的にアプローチします。採用マーケティングは、既に確立された採用ブランディングの上に構築され、それを基に施策が展開されます。
具体的には、求人広告、SNS、求人メディア、メルマガなどが含まれます。また、候補者の情報を分析し、最適な候補者に訴求するための戦略を立てます。
| 役割 | |
|---|---|
| 採用ブランディング | 事業戦略に合わせた人材獲得を目指し、企業の価値観を伝え、そのコンセプトに惹かれる人材を引き寄せることで、長期的な貢献と定着を促進 |
| 採用広報 | 企業のポジティブなイメージや職場環境を広く伝え、企業が求める人材を惹きつけるために行う広報活動 |
| 採用マーケティング | ターゲットとなる候補者を引きつけて、応募者数の増加と最適な候補者の獲得を目指す |
採用ブランディングのメリットは?

採用ブランディングを行うことにより、企業の「採用力」を強化するだけでなく、さまざまなメリットがあります。
以下で採用ブランディングを実施するメリットを紹介します。
企業のビジョンや価値観に共感する人材を採用できる
企業のビジョンや価値観に共感する人材を採用できる
採用ブランディングを行うことで、採用後のミスマッチが大幅に減少することが期待されます。ミスマッチが発生する主な原因は、求職者が企業について持っていた期待と実際の職場環境との間にギャップが存在することにあります。特に企業文化や職場の雰囲気、仕事の内容に関する誤解が、早期離職に繋がることが多いです。
採用ブランディングを通じて、企業の目指す方向性や価値観を明確にし、共感する人材を惹きつけることができます。
完全にすべてのミスマッチを避けるのは難しいものの、求職者は入社前に企業が提供するリアルな情報を確認し、ミスマッチが起きていないか事前に理解できるため、入社後に感じるギャップが最小限に抑えられます。
結果として社員の定着率の向上が期待されます。
採用コストを削減できる
企業のウェブサイトやSNSなど自社のプラットフォームから直接応募が増え、広告や人材紹介会社を利用する必要が減り、これまでに比べて大幅なコスト削減を期待できます。
さらに、企業の理念やカルチャーに合った求職者が増えることで、書類選考や面接の負担が軽減され、選考段階の時間的コストも削減されます。企業文化にマッチした人材は離職率が低いため、早期退職による再採用の必要が減少し、採用コストの削減につながるのです。
既存社員のエンゲージメントが向上
エンゲージメントの向上には、従業員が企業の文化や価値観に深く共感し、自身の仕事が組織全体の目標にどのように貢献しているかを理解している状態が求められます。
採用ブランディングを行うことで、従業員は自分が働く意味と企業が目指す方向性をより明確に理解することができます。これが、従業員のモチベーションを高め、より積極的に業務に取り組む姿勢を促します。また、企業の価値観に共感した方が多い職場環境は、社員間のコミュニケーションも自然と増え、職場全体の士気を高める効果もあります。
採用ブランディングのデメリットは?

採用ブランディングは多くのメリットがある一方でいくつかのデメリットも存在します。
どのようなデメリットがあるのか、ご紹介します。
効果が出るまでに時間がかかる
採用ブランディングのデメリットの一つとして、効果が現れるまでに時間がかかる点が挙げられます。
企業の文化や価値観を伝えるためには、魅力的なコンテンツの制作と、ブランディングに沿った情報を一貫して発信する取り組みが大切です。効果を感じるまでには、通常2〜3年の時間を要することが多く、採用ブランディングは継続的な取り組みを前提としています。
企業全体で協力して進める必要がある
採用ブランディングは単に人事部門のみの取り組みではなく、マーケティング、経営層、さらには現場の従業員に至るまで、企業全体のコミュニケーションが求められます。
特に大きな組織では部門間のコミュニケーションの壁や利害の対立が障害となることがあります。各部門が異なる優先順位を持っている場合、採用ブランディングの取り組みを組織全体で一致団結して推進することが困難になることも少なくありません。その結果、採用ブランディングの効果が最大限に発揮されないことや、プロジェクトの進行が遅れることが起こり得ます。
そのため、採用ブランディングの成功には、企業全体でのオープンなコミュニケーションが非常に大切です。
採用ブランディングの進め方

採用ブランディングは、企業が理想の人材を引き寄せるために非常に有効な戦略ですが、その実施には計画的なアプローチが必要です。ここでは、採用ブランディングの進め方について詳しく解説します。
ステップ1:自社の強みと魅力を洗い出す
採用ブランディングを進める第一ステップは、自社の強みと魅力を明確にすることです。
- 企業文化
- キャリアの成長機会
- 仕事内容や働き方
- 福利厚生
- 職場の雰囲気
- 企業の強み
- 企業のサービス
- 経営者
これらの要素を深く理解し整理することで、自社の魅力を再認識し、競合他社との差別化ポイントを洗い出すことができます。自社が持つ価値や特色を正確に把握し、活かすことが、採用ブランディングの成功に直結します。
ステップ2:競合調査
競合他社の採用ブランディングの強みと弱みを分析します。調査するには競合他社の採用ページ、求人広告、SNS、社員インタビューなどを確認すると良いでしょう。これらの情報から、競合がターゲットにしている候補者、職場の雰囲気、働き方の特徴、企業文化などを把握することができます。
次に、これらの情報を用いて、自社が競合とどのように差別化できるかを把握します。また、競合が見落としている可能性のある特定の市場に焦点を当てることも一つの戦略です。
併せて、自社の訴求を競合他社と比較することも大切です。競合他社がどのようなアプローチで求職者にアピールしているかを把握し、必要に応じて自社の訴求ポイントを見直しましょう。
ステップ3:ターゲット人材を決める
次に「どのような人材を求めているのか」を具体的に定義することが重要です。通常、採用ターゲットは一般的な属性情報で表されます。例えば、「営業職の25〜30歳、首都圏在住」などです。しかし、年齢や職種、居住地の情報だけでは不十分です。より効果的な採用を行うためには、候補者のライフスタイル、性格、スキルセット、そして仕事に対する価値観や期待を含む、より詳細なペルソナを定義することが必要です。
ペルソナを細かく設定することで、採用チーム全員が同一の人物像を念頭に置きながら、一貫性のあるメッセージを発信することが可能になります。
ペルソナを作成する際に最低限必要な項目をまとめました。
- 年齢
- 職種
- 居住地
- 性格
- ライフスタイル
- スキルセット
- 仕事に対する価値観
- キャリアの目標
ステップ4:採用コンセプトを決める
採用ターゲットのペルソナを定めた後、次に行うべきは「採用コンセプト」の設定です。企業はどのようなメッセージで求職者にアプローチし、市場で自社をどのように位置づけるかを定義します。
採用コンセプトを作成する際、企業はまず自社の独自性や差別化ポイントを強調するコアメッセージを策定します。これは、自社の文化、目指すビジョン、提供する機会などを踏まえた上で、ターゲットとする求職者に響くように設計されるべきです。目を引くキャッチコピーを考えるだけでなく、「応募者に対して自社の強みをどのように発信するか」をチームでコミュニケーションを取り、アイデアを出し合うことが推奨されます。
次に、このコンセプトを具体化するために、使用するビジュアル、言語、ストーリーテリングの方法を選定します。ビジュアルでは、企業のロゴ、色使い、フォントスタイルが一貫性を持ち、企業イメージに適合する必要があります。言語に関しては、対象求職者に共感と興味を喚起する魅力的なコピーを使用すると良いでしょう。
ペルソナと採用コンセプトに矛盾があると、情報発信の方法や内容、候補者との接点作りに不整合が生じ、本来伝えたいメッセージが届かない恐れがあります。そのため、採用コンセプトを定める際にはペルソナとの整合性を保ちつつ、慎重に策定する必要があります。
ステップ5:発信方法を決める
コンセプトを定めた後、次に企業がどの媒体で求人情報を発信するかを決定します。企業の採用ページ、SNS、求人広告、業界イベントやキャリアフェアなど、様々なプラットフォームが存在します。各媒体の特性を理解し、自社の目的に最も適したものを選ぶことが重要です。
発信方法が決まったら、それぞれのプラットフォームにかかるコストと運用リソースを確認しましょう。
採用ブランディングを成功させるためには、予算と運用リソースを考慮しつつ、複数のプラットフォームをバランスよく利用することが望ましいです。一般的に、2〜3つの異なるメディアを組み合わせることで、より広範囲の求職者にアプローチできます。
ステップ6:社内の協力体制を整える
採用ブランディングは人事部門だけの仕事ではなく、企業全体の取り組みとして扱う必要があります。社内の様々な部門やチームでコミュニケーションを取り、一貫したブランドメッセージを外部に発信することが重要です。
経営層をはじめとする社内のリーダーたちが採用ブランディングの重要性を理解し、積極的にコミュニケーションを取りながら各部門で協力することが必要です。経営層が採用ブランディングの取り組みをサポートすることで、社内の様々な部署が協力して取り組む状態を作り出せます。
ステップ7:効果検証・改善
施策を実行して終わらせるのではなく、実施した採用ブランディングの成果を評価し、必要に応じて改善策を講じることが重要です。
新規応募者数、サイトのトラフィック、求人広告のクリック率、SNSのエンゲージメント、オファー受諾率などの指標を用いて効果を測定します。次に、収集したデータとフィードバックをもとに、採用ブランディング戦略のどの部分がうまく機能しているか、または改善が必要な媒体はどこかを分析します。例えば、特定のチャネルからの応募が少ない場合、そのチャネルの利用方法やメッセージの内容を見直すことが考えられます。
また、改善策を検討する際は、新たな入社者のフィードバックやエージェントからの意見を参考に課題を洗い出すのも有効です。
採用ブランディングにおすすめの発信手段は?

現代の採用市場には多種多様な発信手段が存在し、どのプラットフォームを選ぶかは採用担当者にとって頭を悩ます問題かもしれません。
ここでは特におすすめの発信手段を紹介します。
ただし、最終的に自社の採用ターゲットに最も合致する媒体を選ぶことが重要です。各媒体の特性を理解し、それが自社の採用戦略にどのようにフィットするかを検討することで、最適な採用ブランディングを実施することができます。
自社の採用サイト
採用ブランディングにおいて最も重要な役割を担うのが、自社の採用サイトです。会社の魅力を発信するためには、洗練されたデザインと充実したコンテンツが必要です。
また、会社の理念やミッション、ビジョン、価値観をはじめとするブランドイメージを伝える内容は必須で、さらに、入社後の働き方や福利厚生、キャリアアップの機会、研修制度についても詳細に説明します。また、現在の従業員のインタビューを掲載することで、リアルな職場の雰囲気が伝わり、サイトの説得力が増します。
さらに、採用サイトを検索エンジンに最適化することで、自然検索からの訪問者数を増やすことができます。適切なキーワードの使用やコンテンツの質を高めることで、求職者が自社のサイトを見つけやすくなります。
オウンドメディアや採用ブログ
オウンドメディアや採用ブログでは、会社のイベント、従業員のインタビュー、職場環境、キャリア成長の機会など、多岐にわたるテーマを取り扱うことができます。求職者は社員間のコミュニケーションの雰囲気を感じ取りながら、詳細に会社の情報を得ることができます。
採用ブログは自社ドメイン内で作成することが多いですが、最近ではnoteやWantedlyなどの外部メディアを活用する企業が増えています。外部メディアを利用する最大のメリットは、そのプラットフォームが持つ集客力を利用できる点にあります。
SNS(LinkedIn・X(旧Twitter)、Facebook・Instagramなど)
採用ブランディングにおいて、SNSは求職者と直接コミュニケーションを取るための非常に強力な発信手段です。特に、求職者とのダイレクトなコミュニケーションを可能にし、企業文化や働く環境の魅力をリアルタイムで共有できます。
近年では、求職者が職場の様子をSNSを通じて企業の情報を把握することが一般的になっています。また、多くの企業が採用専用のアカウントを持ち、情報発信を行っています。
動画コンテンツ(YouTube・TikTok)
採用ブランディングにおいて、動画は非常に有効な発信手段です。文章に比べて動画は、より多くの情報を共有でき、視聴者により企業の印象を残すことができます。
近年では、ショート動画だけでなく、社員インタビューや日常業務の様子を収めた動画をYouTubeに投稿する企業が増えています。求職者は企業の文化や職場環境を理解しやすくなり、企業がどのような価値を大切にしているのか、実際の働き方はどのようなものかを直感的に捉えることができます。
視覚的な印象は強く残りやすいため、動画は企業が求職者の記憶に長く留まるブランドイメージを築くのに役立ちます。
求人プラットフォーム(Wantedlyなど)
新卒採用では就活ポータルサイト、中途採用では転職情報サイトの使用が一般的で、これらのプラットフォームは求職者が積極的に情報を求めて訪れる場所です。そのため、企業は自社の魅力をダイレクトに伝え、適切な候補者にリーチすることができます。
最近のトレンドとして、単なる求人情報の掲載だけでなく、企業の文化や働く環境を紹介するための記事や動画を含められるメディアが増えています。
それぞれのプラットフォームは異なるターゲット層にリーチするため、企業は自社の採用ターゲットに最も合ったメディアを選ぶことが重要です。
採用ブランディングに成功した企業の事例

採用ブランディングに成功している企業は、どのような施策を講じているのでしょうか?
優れた人材を惹きつけ、組織に長期的に貢献してもらうためには、採用ブランディングが不可欠です。ここでは、いくつか採用ブランディングの成功事例を紹介し、それぞれの企業がどのような方法で自社の情報を発信し、理想的な候補者を引き寄せているのかを解説します。
株式会社SmartHR
株式会社SmartHRは、独自の採用ブランディングを通じて、わずか1年で約3,700人のタレントプールを形成するという顕著な成果を達成しました。同社は採用人数の増加に伴う母集団不足という課題に直面していましたが、人材紹介に依存する従来の方法から脱却し、多様な採用チャネルの強化に着手しました。
SmartHRは、求職者が最初に接点を持つ段階から応募に至るまでのプロセスを4つのステップに分け、それぞれのステージでのストーリーラインを丁寧に設計しました。求職者に対して一貫したメッセージを発信することができ、企業の魅力をアピールしたのです。
また、発信コンテンツとしては、代表者と社員のブログ、社内報、外部メディアによる社員のインタビュー記事など、多面的なアプローチを採用。実際に働く社員の人柄や職場の雰囲気をリアルに伝えることに力を入れました。さらに、実際の職場の雰囲気を体感してもらうためのイベントを開催することで、求職者とのより深い関係を築き、採用ブランディングの成功につなげました。
株式会社メドレー
株式会社メドレーは、採用ブランディングにおいて、企業のフェーズに応じたコミュニケーションで顕著な成果を上げています。
メドレーの採用ブランディングの第一段階は、自社を「医療×ITのリーディングカンパニー」として業界に位置づけることに焦点を当てました。この目標達成のために、同社はWantedlyのストーリー機能を活用して「私がメドレーに入社した理由」というシリーズを連載し、120万近いPVを記録しました。
認知度が確立された後、メドレーはさらに一歩進んで企業の社会的役割を広く認知させるためのブランディングを展開しました。コーポレートサイトの全面改訂、動画メディアの掲載をはじめとするコンテンツの刷新を行い、より魅力的な企業イメージを構築しました。
メドレーの採用ブランディングの成功は、「何を伝えたいか」を明確にし、それに基づいたコンテンツを体系的に配信する方針によるものです。
各社員がこのビジョンを共有し、統一されたメッセージを外部に向けて一貫して伝えることで、採用ターゲットとの関連性と魅力を最大限に引き出しています。
株式会社メルカリ
メルカリは、採用ブランディングにおいて企業の独自性と「メルカリらしさ」というブランドイメージを業界に浸透させ、成功を収めています。
メルカリの採用ブランディングは、主にオウンドメディア「mercan」を中心に構築されています。このプラットフォームは、メルカリの文化、社員の物語、そして会社が直面するリアルな課題を正直に共有する場として機能しており、これが多くの読者にリアルで人間味のある企業のイメージを植え付けました。
「mercan」では、ブログ更新の他に、動画やイベントの実況など、多様なコンテンツを通じてメルカリのブランドイメージを形成しています。
採用の成功は、HR部門だけでなく、全社員が採用プロセスに積極的に参加する文化からも支えられています。
採用ブランディングにおいて風評被害が発生した場合は専門業者へ依頼しよう

採用ブランディングにおいては、企業の評判が直接採用の成果に影響を与えるため、風評被害には早急に対処する必要があります。例えば、Googleサジェスト(検索バーに入力を始めたときに表示される予測キーワード)などに「〇〇企業 ブラック」といったワードが表示されると、潜在的な応募者に悪い印象を与えかねません。
根拠のない風評が浮上した場合、風評対策を専門に行う業者や弁護士に相談することが推奨されます。
専門業者や弁護士は不適切または事実無根のワードが検索候補に表示された際に削除、または出現しないように対策をすることが可能です。
採用ブランディングにおいて風評被害は避けたいため、こうした対策も忘れてはなりません。
まとめ
採用ブランディングは企業が理想の人材を惹きつけ、採用後も長期にわたり貢献してもらうために不可欠です。
採用ブランディングを成功させるためには、採用コンセプトを決め、企業のカルチャーや価値観、職場の魅力を明確に伝え、ターゲットとなる人材に合わせたアプローチが求められます。さらに、採用ブランディングは人事部門のみの取り組みではなく、企業全体のコミュニケーションが求められます。
また、定期的な効果検証と戦略の見直しを行い、市場の変化や組織のニーズに柔軟に対応することが重要です。
風評被害などの予期せぬ問題にも対処するための対策を整えておくと良いでしょう。